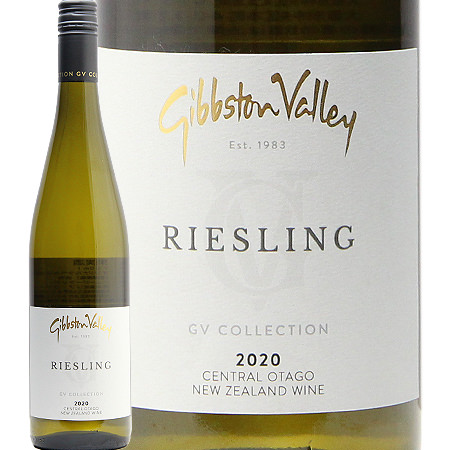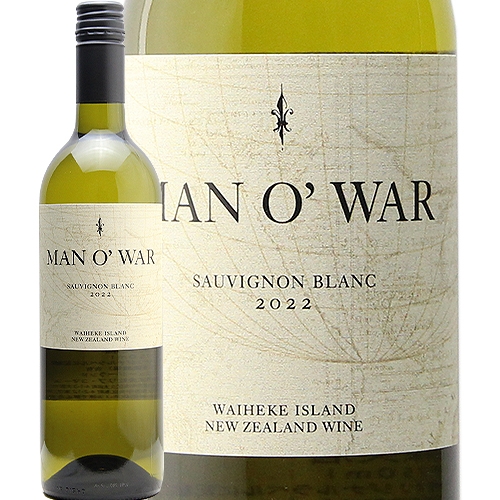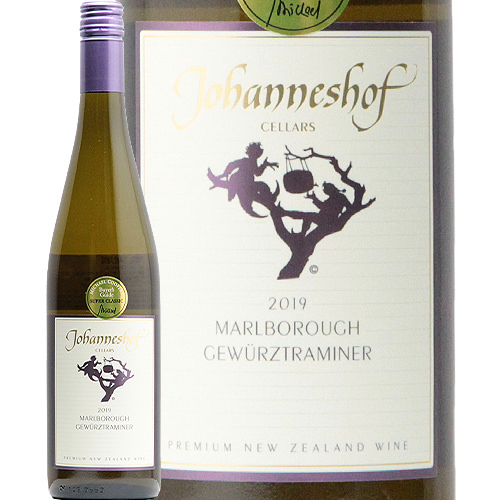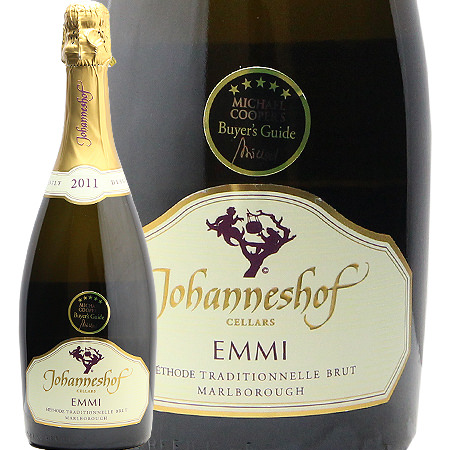一人のワイン好きサラリーマンが、脱サラしてニュージーランドワインのインポーター社長に。そのワインの魅力を「ワイン初心者でも親しみやすいわかりやすさ」だと語ります。現地の滞在経験をもとにその魅力を伝える、リブ・コマース山下さんにインタビューしました。その熱い想いが10%でも伝われば、ニュージーランドワインが飲みたくて仕方なくなることでしょう。
山下さんが語るニュージーランドワインの魅力とは
「ワイン初心者に選びやすく分かりやすい」
それがニュージーランドワインの魅力であると、山下さんは自身の経験をもとに語ります。

有名単一品種のワインだから選びやすい
ワイン初心者のほとんどが直面する難題が、「何を飲んでいいのか分からない」です。
なにせワインは種類が多い。スーパーであっても何十種類と並んでいる。名前も小難しくて意味が分からない。好みの味とそうでないものがあるのは分かるけど、それをどう言葉にしていいか分からない。好みのワインと似たものを選ぶ方法も分からない・・・・。

その選択ストレスを軽減する第1歩が、「ブドウ品種でワインを選ぶ」です。
ブドウ品種はワインの風味を決める最重要要素の一つです。メジャーな品種の典型的なワインを飲み比べ、その中で自分の好みに近いものを選ぶ。その品種名を頼りに、ワイン売り場で予算にあわせてワインを購入する。
これが最も単純明快な、「自分でワインを選べるようになる」第1歩です。
その点でニュージーランドのワインは、単一品種でつくるワインが比較的多い。だから「ピノ・ノワールって何?」ってところからスタートしても、短期間で「私はこの品種のワインが好き」と選んで買えるようになるのです。
分かりやすい味わいのワインが多い
ブドウ品種でワインを選ぶなら、その品種の特徴的な味わいを期待します。ところがあるブドウ品種を100%使用しているからといって、その教科書的な味わいがきっちり現れているとは限りません。
その理由の一つが醸造法。例えば過熟気味のブドウを使ってオーク樽熟成の風味を存分に利かせれる。香り豊かで濃厚なワインはつくれるでしょうが、品種や産地の風味は相対的に違いを感じにくくなります。極端な話、カベルネ・ソーヴィニヨンでもメルローでもだいたい同じ味になってしまいます。

あるいは近年話題の「ナチュラルワイン」の大部分。「添加物を極力なくし、なるべく人の手を加えないようにつくる」という醸造方法が先行してしまった場合、品種や産地が違っても似通った風味のワインが生まれます。その是非は置いておくとして、「品種の特徴からワインを選ぶ」という点では不適切。知識として学んだ特徴をワインに感じられないからです。
そういったワインが、ニュージーランドには比較的少ない。きちんと品種特性が表れたワインが多いのです。少なくとも日本に輸入されて私が口にしたことのある中では、そういう傾向が強いです。
ブドウ品種で選びやすいワインの産地だから
単一品種でつくり、その品種特性を素直に表現したワインが比較的多い。
それが「ニュージーランドワインが初心者におすすめ」と言われる理由です。

もちろんそれはニュージーランドだけではありません。
アメリカも単一品種のワインが多いです。ただ、樽香が強く香る醸造特性が現れたワインも多いです。
オーストラリアも単一品種のワインが多いうえ、手頃なワインも多いです。ただ、品種の選択肢はニュージーランドより多く、それが迷ってしまう要因になるかもしれません。
となるとチリや南アフリカが強力なライバルと言えるのは間違いないでしょう。
山下さんがこう魅力を語るのは、自身がワイン初心者であるとき、ニュージーランドワインは非常に学びやすく分かりやすいと感じたからです。
リブ・コマース 山下さんについて
全く違う業種の際にニュージーランドワインに出会って学び、それから紆余曲折を経て脱サラ、ワインインポーターとなった。
山下さんの経歴を知ると、「お酒の神様バッカスのお導き」なんて言葉が頭をよぎります。
ドーナツ屋さんとしてニュージーランドに住む
山下さんが大学卒業後に就いたのは、精密機器の営業販売の仕事でした。途中からは海外に駐在しての営業。その時代に輸出入のノウハウを習得できたことが、今の仕事にも活きているといいます。
リブ・コマースさんが輸入するワインは、現地価格と比べてそう高くありません。現地より安いことはないにせよ、他のインポーターの比率と比べて低め。これは当時のノウハウが関係しているのではないでしょうか。

海外駐在の経験をもとに次に就いた仕事が、アメリカのドーナツチェーンをニュージーランドで展開する仕事。このために数年間ニュージーランドに住んでいたといいます。
ニュージーランド人は朝早くから働く代わりに、長時間労働はしないそうです。なので夜時間が余る。そこで当時から好きだったこともあり、現地のワインスクールに通い始めました。
品種で世界と比較して学ぶ
当時の先生はボブ・キャンベルMW。ワイン業界の最高権威であるマスター・オブ・ワイン(MW)の称号に、ニュージーランドで初めて認定された人物です。
彼が開催するアマチュア向けコースに通い、当時はあくまで趣味としてワインを学んだそうです。
マスター・オブ・ワインについてはこちらの記事で詳しく▼
そこで教わったのがブドウ品種からワインを理解すること。まずはフランス、イタリア、ドイツといった主要国から始まり、ニュージーランドワインと品種ごとに比較します。
ニュージーランドには土着品種というものがありません。基本はフランス系の国際品種です。だからこそ比べることで共通点であり特徴を理解しやすい。
知識で学んで鼻と舌で感じる授業が、「勉強がすごく入りやすかった」と語ります。
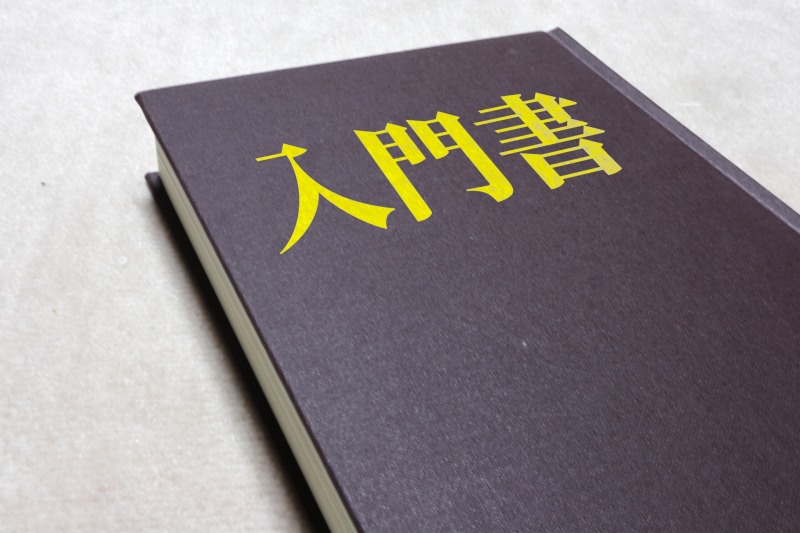
「分かりやすさはニュージーランドの強さ」これを実体験として強く感じたのです。
その授業の一環として、「クメウ・リヴァー」なども訪れたそうです。ニュージーランドのシャルドネとしては、おそらくトップ評価を受ける生産者です。
「教科書に出てくるワインをつくっている世界レベルのワイナリーに、ちょっと足を伸ばせば訪問できる」
これはワイン生産国で勉強する大きなメリットだと言えるでしょう。うらやましいです。
大阪で働きリブ・コマースを引き継ぐ
ドーナツの仕事のあと、アメリカでの大学院生活を経て、大阪のとある大手企業に就職します。そこで出会ったのがリブ・コマースです。
実はリブ・コマースは山下さんが設立した会社ではなく、2011年に「デスティニー・ベイ」というワインを輸入するためだけに創業された会社でした。山下さんはそこに加わり、後に株式も含めて買い取って代表となったのです。
ワインビジネスは未経験。2018年に手探りで始めるのは、なかなかのチャレンジだったと言います。
それはたまたまでもあり、完全なる偶然でもありません。デスティニー・ベイは山下さんがニュージーランドにいたころからよく知っていたワイナリーだったのです。
世界が驚いたデスティニー・ベイ
デスティニー・ベイを知ったのは、ニュージーランドで暮らしていたころ通っていたワインショップにて。そこが、ニュージーランドで初めてデスティニー・ベイのワインを取り扱い始めたショップだそうです。
山下さんがニュージーランドに住み始めた前年あたりから、デスティニー・ベイは話題に上り始めていました。
デスティニー・ベイについてはこちらの記事で詳しく▼
デスティニー・ベイとは
リブ・コマースさんにとって最重要ブランドであるデスティニー・ベイ。オークランドがバカンスに訪れる「ワイヘケ島」にあるワイナリーです。
アメリカ出身のスプラット夫妻が旅行でこの地を訪れた際、この雰囲気にほれ込みます。ワインづくりに素晴らしく適した場所であることがわかると、「完璧以外のワインは許されない」と、大学でワインづくりを学んで移り住みます。


つくるのはカベルネ・ソーヴィニヨン中心のボルドーブレンドである3種類のみ。そのトップキュヴェである「マグナ・プラミア」は、「ニュージーランドで最も高価なワイン」として、ソムリエ教本でも紹介されていました。
エントリークラスの「デスティナイ」でも約2万円という高級品です。
ワインアドヴォケイトとジェラール・バッセが評価
デスティニー・ベイのファーストヴィンテージは2005年。その「マグナ・プラミア2005」がワインアドヴォケイト誌にてパーカーポイント90点を獲得しました。(後のレビューで94点の評価もつきました)
数字自体は大してすごく感じないかもしれません。しかしニュージーランドのワインでは、カベルネ・ソーヴィニヨン主体のワインとしてファーストヴィンテージからパーカーポイント90点以上を獲得した、唯一のワインだそうです。
更に2010年、故ジェラール・バッセ氏がデスティニー・ベイを訪れます。マスター・オブ・ワインでありマスター・ソムリエ、2010年の世界最優秀ソムリエ。そんなとんでもない肩書を持つ伝説の人物です。
ジェラール・バッセ氏については、WINE REPORTで詳しく紹介されています。
彼は当時、エリザベス女王の専属ソムリエをしていました。その際に、とあるボルドーブレンドのコレクターがきっかけで、王室にデスティニー・ベイの2006年が入り、彼が飲んだそうです。そこで興味を持った彼はニュージーランドを訪れ、2006~2008年のそれぞれ3種類のワインを全て試飲。
「これはとんでもないワインだ!」とジェラール・バッセ氏が評価したことがきっかけで、世界にその名前が広まっていったそうです。
日本にはその1年後の2011年から入ってきているのですから、当時から目をつけていた創業者には敬服します。
ワインショップを通して出会う
山下さんがニュージーランドに滞在したのは、ちょうどデスティニー・ベイが有名になってきたときから。いきつけのワインショップを通して知ったそうです。
デスティニー・ベイのショーン・スプラット氏と知り合ったのも当時から。ワインの仕事をする前からワイナリーに訪問していたそうです。


それから数年後、ワインビジネスを始めて輸入業者となるのですから、人の縁がどこでつながるかわからないものです。
デスティニー・ベイが素晴らしいワインであることは間違いありません。しかし最低2万円のワインでは、扱えるお店が少なすぎてインポーターとしての事業が成り立ちません。そこで取り扱いワインを増やすべく、山下さんは買い付けのために再びニュージーランドを訪れたのでした。
専門インポーターとしての勝ち筋
ニュージーランドに限らず、いくつもの国のワインを輸入する選択肢もあったはずです。
それでもニュージーランドのワインを選んだのは、一つは滞在経験から土地勘があったから。
しかしそれだけではありません。ニュージーランド国内で高く評価されているワイナリー。その中に未だ日本に輸入されていないものがたくさんあると知っていたからです。
ニュージーランドワインのバイブル
日本に輸入されていないワインから、自社が取り扱うものをどう選ぶべきか。
その際に参考にしたのが、レベッカ・ギブズMW著の「The Wine of New Zealand」というガイドブックでした。
ニュージーランドワインに関することを総合的に書いた本で、気候や歴史などとともにワイナリーも紹介されています。
Amazonのサイト▼
ここで「Must Drink」として挙げられていたワインが、不思議とまだ日本に輸入されていませんでした。訪れてみると2つ返事で「いいよ!」と契約できたそうで、それが今のポートフィリオにつながっています。
以下に簡単にご紹介します。
[マールボロ]アンツフィールド
ラインナップの中では比較的規模が大きめ。「「ザ・ニュージーランド」というようなソーヴィニヨン・ブランをつくっているだけあり、物量的に大きなウエイトを占めます。
リブ・コマースが輸入する際もごくごくわずかに並行品が輸入されていたそうですが、今は独占販売。なぜどこも輸入してなかったのか・・・そう疑問に思うほど、高品質で値段もてごろなワインをつくります。
アンツフィールドについてはこちらで詳しく▼
[セントラル・オタゴ]ギブストン・ヴァレー
セントラル・オダゴで実は最も古いのが、このギブストン・ヴァレー・ワイナリー。サブリージョンの名前である「ギブストン」という名がついていることに、その古さがうかがえます。 (他にはリッポン・ヴィンヤードも古いのですが、リリースはこちらが先)
決して古いだけでなく、そこそこに生産規模もあり、ワインリゾートとしても成功しています。もちろん味も美味しい。抽出がやさしく上品な系統です。
ここも輸入されないままだったというのは驚きです。
[ワイヘケ島]マン・オー・ウォー
ここはデスティニー・ベイとおなじワイヘケ島のワイナリー。ここはブドウ品種も価格帯も幅広くつくっています。ソーヴィニヨン・ブランやピノ・グリといった定番品種はもちろん、ボルドーブレンドやシラーなどでも秀逸なものをつくります。
ラインナップの中で中核からアクセントまで担えるワイナリーです。
※2023年のハリケーンの影響により、当面輸入がストップする予定です。


[マールボロ]ヨハネショフ・セラーズ
ここはアロマティック品種と高級スパークリングワインが素晴らしい!
ニュージーランドでずっとNo.1を取り続けているというゲヴュルツトラミネール。驚きの熟成期間ゆえ、飲めばこの価格も安いと感じさせてくれる瓶内2次発酵のスパークリングワインに注目です。
ただし生産量が少ないので、それが手つかずだった理由でしょう。
[ホークス・ベイ]コラボレーション・ワインズ
ガイドブックの中で「今注目の女性生産者」として大きく紹介されていたというのが、この「コラボレーション・ワインズ」
かなりの小規模生産であるため、安定的に供給できるものではなく、また価格も少し高めです。それでもジュリアンヌ・ブローデン氏がつくるこの上なく繊細なタッチのワインは、ラインナップの中で替えが効くものではなく、いいアクセントになっています。


山下さんの商品戦略
ここまでご紹介したのが、山下さんがリブ・コマースを受け継いでから取引を始めた初期のワイナリー。それからも新しいワイナリーは開拓中だといいます。現地の展示会などに参加して選ぶこともあるとか。
その中で大事にしていることは、「まずニュージーランド内での評価が高く、味も素晴らしく、ストーリー性のあるワイン」
そういったワインを仕入れるのが、商品戦略だと語ります。
山下さんが本当は仕入れたいワイン
いくら取り扱いたいというワインがあっても、既に日本に輸入されている場合もあります。
他社の宣伝になって申し訳ないなと思いながらも、紹介してもらいました。
スパークリングワインなら本当はここ!
セントラル・オタゴでスパークリングワインやピノ・ノワール、シャルドネをつくる「クオーツ・リーフ」。ツアーで現地に行った際に、スーパーなどで普通に売ってるので、お土産としておすすめしてたほどだとか。
特にスタンダードなスパークリングワインがコスパいいそうです。
ワイナリー公式HP▼
ジェロボームさんHP▼
本当は面白いことやっている!
もう一つ挙げるならマールボロの「フォレスト・ワインズ」。
現在輸入されているのは数種類ですが、輸入されていないワインが面白い。白のブレンドやアルバリーニョ、シュナン・ブラン、サン・ローラン、レイトハーベストなど様々なワインをつくっているそうです。
ここは輸入に向けて交渉を進めていたのに、残念ながら中間業者の事情で契約できなかったとか。
公式HP▼
フィラディスさんHP▼
ニュージーランドワインの今とここから
ニュージーランドはワインにおいても市場においても、特にサスティナブルな取り組みに関心の高い国です。
オーガニックを実践する、農薬を使わないなどから一歩進んだ取り組みを始めているといいます。
型にとらわれないサスティナブル
例えば除草作業について。
畑に雑草が茂ると土壌の栄養が取られ、湿度が上がって病気になりやすくなります。対策として手っ取り早いのは除草剤を撒くことですが、それでは土の状態が悪くなってしまうことがわかってきました。
そこで導入事例をよく耳にするのが、羊や山羊などの動物に草を食べさせること。


ただしこれも実は良し悪しがあるそうです。
動物が草を食べれば糞をします。それが土に窒素を供給します。きっと程度の問題でしょう。それが多すぎるとブドウの木が弱って、ブドウの糖度が上がり切らないなどの問題が起こるそうです。
現在のニュージーランドではやらないのが主流だとか。
ボルドー液の使用についてもです。
ボルドー液は硫酸銅と生石灰を混合した溶液で、非常に昔からブドウの病害対策に使われてきました。これはオーガニックやビオディナミなどの農法でも許可されています。
ただし他の農薬を使わないゆえボルドー液の使用が増え、土壌に銅が蓄積するという問題も表面化しています。
極端な例としてデスティニー・ベイでは、ボルドー液を使うと翌年の木の状態が非常に悪くなると言います。ここではボルドー液の代わりに天然成分由来の防除液を使っているのだとか。
単に禁止薬剤を使わないというのではなく、畑にとってどんな農法がベストなのかを研究した上で、自然に寄り添った選択をしている。それを山下さんは「諸外国のサスティナブルな取り組みから、もう一歩進んでいると感じる」と話します。
政府がサポートするサスティナブル
「人間がいて自然がまわらないといけない。だからサスティナブルに共存できる形をつくろうよ」
その取り組みを国家的にまわしているプロジェクトがあるのが、ニュージーランドの強みだといいます。
例えば温室効果ガス。
その年にどれほど温室効果ガスを排出して、どれほどのワイン・ブドウを生産したか。そのレポートを全ワイナリー・全ブドウ栽培者が提出しています。そうしてサスティナブルな取り組みを「見える化」しているそうです。
市場に浸透しているサスティナブルな意識
ワインを生産する側だけでなく、消費する側もサスティナブルに関心が高いそうです。もちろんワイン以外も。
例えばゴミの分別はかなり厳しい。生ごみをコンポスト化する仕組みが普通の賃貸物件にもついている。ナイロンのレジ袋はほとんど使わないなど。
そんな社会の中でワイン生産者・醸造家というのは、比較的高収入な仕事だそうで、学力のある人が働いているといいます。
それが世界的に見ても新しい技術に基づいたワインづくりを支えているのでしょう。
ニュージーランドワインのこれから
ニュージーランド国内では、ブドウ品種やクローンの研究・技術開発が目覚ましいそうです。
それは「次はこの品種がトレンドになる」というような短期的なものではなく、もっと中長期的に考えられているのだとか。
生産者の中では、もはやあまりソーヴィニヨン・ブランの話はされないとか。


その上で今注目すべきは、カベルネ・フラン、シュナン・ブラン、アルバリーニョ。これらで良いものがたくさんつくられ始めているので、輸入していきたいと考えているそうです。
新品種に積極的かどうかは産地によって温度差があるとか。
積極的なのはネルソン、オークランド、ホークス・ベイ、マールボロ、セントラル・オタゴなど。特に「一番変態っぽい人があつまる傾向がある」というのがネルソンだそうです。楽しみ。
小さなインポーターの魅力
日本には数多くのワインインポーター、つまりワインの輸入業者があります。
その規模は様々であり、ビールメーカー傘下の大企業から、社長さん一人で大部分の業務を行う小規模事業者まで様々。
大規模なインポーターのメリットは数多くあります。一番はそのスケールメリット。同じ価格でワイナリーを出たワインでも、日本にてより安い価格で販売することができます。様々なプロモーションができるなど、いい点を挙げればきりがありません。


一方で小規模だからこその魅力もあります。それはワインを紹介してくださる営業さんがバイヤーも兼ねていること。ワインの味わいの方向性に統一感があります。1本好みのワインがあれば、同じインポーターのワインが口にあう可能性も高いです。自分で探してきたワインを自分で紹介しておすすめするからこそ、紹介に熱意が乗ります。
それだけではありません。買い付けを担当するということは、必ず数多くの採用しなかったワインがあります。味や価格を知ってなお選ばなかったワインもあるからこそ、そのワインを選んだ理由が明確です。
おすすめするワインを知っているだけでない、おすすめしないワインとの違いを知っているからこその説得力があるのです。
次にワインを飲む際は、ぜひバックラベルに書かれているインポーターにも注目してみてください。そこが名前の通っていない小さなインポーターであるほど、インポーターでワインを選んでみる楽しみがあるかもしれません。