
近年非常に勢いがある「日本ワイン」。「国産ワイン」との違いをあなたは知っていますか?制度に基づいた明確なルールは、つくり手を守るとともに、消費者が選びやすいことが目的です。現在5つ認定されている地理的表示(GI)は、まず注目すべき産地とワインを示しています。ここ10年少々で驚くほど洗練された日本ワインには、輸入ワインとは少し違った楽しみ方が見つかるはずです。
そもそも「日本ワイン」と「国産ワイン」は何が違うの?
「国産ワイン」というのは今は正式な名称ではなく、「国内製造ワイン」と言います。
「日本ワイン」との違いは、日本ワインはブドウの生産地です。「国内製造ワイン」は輸入原料を使うこともできるのです。
このような表示ルールを管理しているのは国税庁で、日本で販売されるワインは次の3つに分類されます。
(1)日本ワイン (2)国内製造ワイン (3)輸入ワイン
「日本ワイン」は日本産ぶどうを使った国内醸造ワイン
「日本ワイン」とは、日本国内で収穫されたぶどうを原料とし、日本国内で醸造されたワインのこと。つまりぶどうの栽培からワイン造りまで、すべてが日本で完結していることを示します。
この定義は2018年の国税庁のルール改正によって明確にされ、ワインラベルにも「日本ワイン」の表記が可能になりました。消費者はこの表示を目印に、輸入原料は使用しない高品質なワインを購入できるのです。
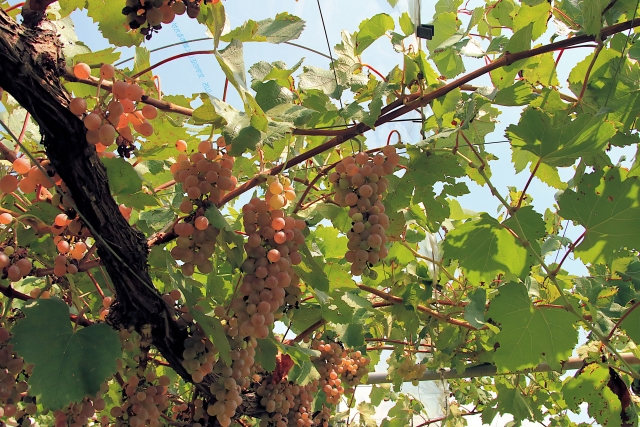
それまでは明確な表示ルールがなかったので、「国産ワイン」のようなまぎらわしい表記もありました。それが明確にルール化されたことで、コストをかけて日本のブドウだけでワインをつくる生産者の優位性が守られるのです。
「国内製造ワイン」はコストダウンのため
「輸入原料を使うから美味しくない」とは必ずしも言い切れません。しかし輸入原料のみ、あるいは輸入原料と国内のブドウからワインをつくるのは、基本的に安く仕上げるため。ゆえにそれほどの品質は望めないのです。
輸入ワインは、1本1本ガラス瓶に入れて輸送されるのが通常です。瓶は割れやすく重たいので、製造コストも輸送コストも高い。なるべくコストダウンするためには、ブドウ果汁やワインを大きなタンクに入れて輸送すればいいのです。果汁の状態なら、フルーツジュースに使われるような濃縮還元の技術が使え、より低コストになります。

スーパーなどで見かける紙パックに入ったワインは、ほぼ国内製造ワインです。輸入ワインと比べて非常に安いのは、そういったコストダウンの工夫がされるからです。手頃な居酒屋で提供されるグラスワイン赤・白も国内製造ワインである例が多いでしょう。
実はまだまだ多い国内製造ワイン
日本で最も多くワインがつくられる都道府県はどこかご存知ですか?実は1位栃木県、2位神奈川県なのです。全くブドウのイメージがないのになぜ?
それは国内製造ワインの大規模な製造所があるからです。
ニュースなどでよく見かけるので日本ワインが多いように錯覚しますが、じつは日本国内でつくられるワインの大半は国内製造ワイン。2020年のデータで日本ワインはわずか18%程度であり、8割以上が国内製造ワインなのです。
2018年制定 「日本ワイン」の表示ルールとは
2018年10月、国税庁により「日本ワイン」の表示ルールが制定されました。 それまで曖昧だった「国産ワイン」との違いが明確になり、日本産ぶどうを使用した高品質なワインが正当に評価されるようになったのです。
表示の信頼性を高めた「85%ルール」
この制度では、産地・品種・ヴィンテージといった情報をラベルに表記するために、以下のような「85%ルール」が定められています。
-
産地表記:表示された産地のぶどうを85%以上使用し、かつ収穫地と醸造地が同一であることが必要。 例:「山梨」など
-
産地が収穫地のみ一致する場合:「〇〇収穫」と表記可能
-
醸造地のみ一致する場合:「〇〇醸造」と表記可能
-
品種表記:単一品種を85%以上使用すれば、その品種名(例:デラウェア)の表示が可能 2品種で85%以上の場合は多い順に2つまで、3品種以上の場合は割合を併記して表記可能
-
ヴィンテージ表記:単一年に収穫されたぶどうが85%以上であれば、その年の表示が可能
これらの基準は、フランスやイタリアをはじめとする主要なワイン産地でも広く採用されており、国際的に通用する制度設計と言えます。 裏を返せば、15%までなら表記外の産地や品種を混ぜることも認められているため、ラベルの読み方にも注意が必要です。
消費者と生産者の信頼を守るために
この制度の導入によって、消費者は「日本ワイン」の文字を目印に、一目で国内原料のみで製造されたワインを選べるようになりました。 これで手間やコストをかけて国産ブドウのみでワインをつくる生産者の努力も、正しく評価されるようになったのです。
「日本ワイン」という言葉が、品質と誠実さの象徴として認識されるための大きな一歩となりました。
そうして日本ワインの製造が増えるにつれて、「日本ワイン」という大きなくくりだけでは足りなくなってきました。そこで登場したのが、「GI(Geographical Indication)地理的表示制度」です。
GI(地理的表示)とは?日本ワインにとっての意義
日本ワインの品質向上と多様性が注目される中、GI(Geographical Indication)=地理的表示制度が重要な役割を果たしています。 この制度は、特定の地域で生産された産品の名称を保護し、その品質や特性が地理的な要因に由来することを保証するものです。いわば「産地のブランド化」を国が保証するものです。
GIってなに?他の分野との共通点
GI制度はワインに限りません。例えば「神戸牛」や「夕張メロン」などもGIの制度で保護されています。他の産地の牛肉やメロンを、これらの名称を使って販売することはできません。
GIによって保護されている商品・飲み物は多岐にわたり、こちらのサイトで一覧を見ることができます。
その土地特有の気候や風土、伝統的な製法によって生み出されからこそ美味しい。その信頼がブランドとなり、GI制度によってその名称と価値が保護されているのです。

ワインにおけるGIの目的
GI制度の目的は、ワインの産地や品質をわかりやすく伝えることです。
「このワインは、この土地ならではの味ですよ。こんなに品質が高いですよ」 それがGIの表示が伝えるメッセージです。
GIに認定される道府県は、単に製造量が多いだけではありません。その土地ならではの個性とワインづくりの歴史があるから認定されているのです。
GIは単にその場所でつくられていることを示すだけではありません。その地域自慢のワインと言えるよう、そのスタイルがて定義されています。
日本の地理的特性がワインに与える影響
多くのワイン産地でも産地による区分がなされています。フランスの「AOC」やイタリアの「DOCG」などの制度がその一例です。
有名な生産国に比べると、まだ日本ワインの製造量は僅かなもの。それでもGIを認定する意味はあります。というのも日本は南北に非常に長い地形だからです。

現在日本にはほぼすべての都道府県にワイナリーがあります。沖縄県には1つしかないものの、北海道から鹿児島県までと考えても非常に離れています。その緯度の差は15度。これはフランスのパリとイタリアのローマほどの差があります。
これだけ南北に離れていれば、当然気候が違います。適したブドウ品種も違いが生じ、出来上がるワインにも個性の傾向が生まれます。
だから「日本ワイン」と一括りにするのではなく、「GI山梨」や「GI北海道」のように区別する必要と、分ける価値があるのです。
ワインの産地は細かく分ければいいというものではありません。さして味に違いがないのなら、小難しくなるだけです。明確な違いがあって選び方の指標になるからこそ、産地の区分が意味を持つのです。
2025年現在、日本でGIに認定されている道府県は5つ。認定順に山梨県、北海道、長野県、山形県、大阪府です。こちらは次の章で詳しくご紹介します。
日本ワインの製造量とワイナリー数
最新の国税庁の資料(令和6年)によると、日本国内のワイナリー数は以下の通りです。
|
順位
|
都道府県
|
ワイナリー数
|
|---|---|---|
|
1位
|
山梨県
|
89場
|
|
2位
|
長野県
|
75場
|
|
3位
|
北海道
|
64場
|
|
4位
|
山形県
|
22場
|
|
5位
|
岩手県
|
17場
|
これらのデータからも、GI認定地域が日本ワインの主要な生産地であることがわかります。 一方で、GI未認定の地域でも特色あるワインが生産されており、今後のGI認定拡大や新たなワイン産地の発展にも期待が寄せられています。
一方で大阪府のワイナリー数はわずかに7つで19位。それでも認定されたのには、「産地特性」というものが関係しています。
現在認定されている5つのGIとその特徴
GI(地理的表示)制度は、日本ワインにとって「地域ごとの個性」を示す大切な指標です。 現在、国税庁により認定されているGIワイン産地は5つ。それぞれに、気候や地形、栽培されるブドウの品種やワインのスタイルに明確な違いがあります。国税庁のHPに非常に詳しい特徴と規定があるので、それをかいつまんで要約しご紹介します。
ただしGIに認定された道府県産であっても、GIの申請をせず表記の無いワインもたくさんあります。今回はGI表記のないものでも、その産地の特徴的な品種・味わいのワインを併せてご紹介します。
GI山梨|日本ワイン発祥の地
山梨は量の面においても歴史の面においても日本ワインの中心地。そのためGI認定も最初であり、2013年。「日本ワイン」の名称定義より前のことなのです。
自然的要因
山梨県は、富士山、南アルプス、八ヶ岳、奥秩父などの2,000m級の山々に囲まれた盆地地形で、これにより昼夜の寒暖差が大きく、ブドウの成熟に適した環境です。年間日照時間が長く、降水量が比較的少ないため、ブドウ栽培に理想的な条件が整っています。また、水はけの良い扇状地の土壌も、ブドウの品質向上に寄与しています。
人的要因
山梨県では、江戸時代から続くブドウ栽培の歴史があり、長年の経験と技術が蓄積されています。地元の生産者たちは、甲州やマスカット・ベーリーAなどの品種に適した剪定や棚仕立てなどの栽培方法を工夫し、高品質なブドウを生産しています。さらに、醸造技術の向上にも努め、地域全体で品質管理や技術研鑽を行っています。
ワインの特性
GI山梨のワインは、使用するブドウ品種の特性がよく表れたバランスの良い味わいが特徴です。甲州を使用した白ワインは、柑橘系の香りと爽やかな酸味を持ち、和食との相性が良いとされています。マスカット・ベーリーAを使用した赤ワインは、鮮やかな赤紫色で、華やかな香りと穏やかな渋みが特徴です。
国税庁HPより
GI山梨のおすすめワイン
山梨は歴史の長い産地だけあり、老舗といえるワイナリーが他に比べて多いです。そういったところは品質もさることながら、日常的に飲みたい価格のワインを安定して供給しているケースが多いのが特徴です。ブドウ栽培の歴史が長いので、栽培と醸造の分業体制ができています。
山梨ワインを味わうなら、白は甲州、赤はマスカット・ベーリーAがスタート。
勝沼醸造は山梨における主要生産者の一つ。醸造所のある下岩崎を含む「祝」地区というところのブドウをつかってつくられる甲州がこちら。
商品ページの写真解像度では見づらいのですが、ラベル上部に「GI Yamanashi」の文字があります。
主要なワイナリーの一例
シャトー・メルシャン、サドヤ、サントリー登美の丘ワイナリー、ルミエール、中央葡萄酒、キザンワイン、シャトレーゼ、甲斐ワイナリー、シャトー酒折、キスヴィン、ミエ・イケノなど
マルスワインについて詳しく▼
GI北海道|冷涼な気候で他にない品種
2番目にGI認定されたのは北海道で2018年のこと。ブドウの生育期に雨の多い日本にあって、北海道には梅雨がなく台風もあまり通らないことが、良好な生育環境につながっています。一方で冬の厳しい寒さや大雪の対応が必要であり、栽培は決して簡単ではありません。
自然的要因
北海道のブドウ栽培地は、4月から10月にかけて日較差が大きく、冷涼な気候が特徴です。これにより、糖度が高く有機酸を豊富に含むブドウが収穫できます。また、年間を通じて気温が低いため、ワインの貯蔵温度を自然に低く保つことができ、果実味を維持したまま製品化が可能です。
東部は冬の気温が低すぎて樹が枯れてしまうため、主に道内の西部に産地があります。豪雪地帯のため雪の対策が非常に重要です。
人的要因
北海道では、ワイン事業者の努力に加え、道産ワイン懇談会の活動を通じて、豪雪や厳寒といった気候条件に対応した栽培技術が確立されてきました。さらに、耐寒性に優れたヤマブドウ種やハイブリッド種など、北海道の自然環境に適応した品種の開発も積極的に行われています。
ワインの特性
GI北海道の白ワインは、豊かで華やかな花や柑橘系の香りと、豊かな酸味を持ち、フルーティーで軽快な味わいが特徴です。赤ワインは、スパイスや果実の香り、はっきりとした酸味と穏やかな渋みを備えています。
北海道産のおすすめワイン
その冷涼気候にあっていると考えたのでしょう。北海道には早くからドイツ系品種が持ち込まれており、樹齢の高いケルナーが見つかります。
また近年では余市のピノ・ノワールにも注目が集まっています。
こちらのキャメルファームワイナリーは、輸入食品チェーン店の「KALDI」のグループ企業。イタリアからコンサルタントを招き、非常に整った味のワインをつくります。
近年ではブルゴーニュの「ドメーヌ・ド・モンティーユ」が函館に「ド・モンティーユ&北海道」を解説して話題となりました。
主要なワイナリーの一例
北海道ワイン、ドメーヌ・タカヒコ、平川ワイナリー、山崎ワイナリーなど
GI長野|欧州ブドウに特化した先進的エリア
ここからご紹介する長野県、山形県、大阪府は3つ同時に2021年にGI認定されました。主要品種はコンコードやナイアガラといった食用ブドウですが、メルローやシャルドネといったヨーロッパ系ブドウの比率も高いのが特徴です。「千曲川ワインバレー」のようにワイン特区が制定され、官民一体となってワインづくりが振興されています。
自然的要因
長野県は本州の中央部に位置し、平均標高が1,000mを超える山岳地帯です。ブドウ栽培地の多くは標高500m以上の高地にあり、水はけの良い土壌と昼夜の寒暖差が大きい冷涼な気候が特徴です。これらの条件が、糖度と適度な有機酸を持つ高品質なブドウの生産を可能にしています。
人的要因
長野県では、桔梗ヶ原地域でのメルロー種の栽培成功をきっかけに、欧州系品種の栽培が県内全域に広がりました。平成に入ると、小規模ながら高品質なワインを生産する「ブティックワイナリー」の設立が増加し、県内各地でワイン醸造が盛んになりました。
ワインの特性
GI長野の赤ワインは、濃い色調と骨格のあるタンニン、適度な酸味を持ち、凝縮感の高い味わいが特徴です。白ワインは、ブドウ品種特有の香りが表現され、フレッシュで生き生きとした酸味を備えています。プレミアムワインは、華やかで気品のある香りと厚みのある果実味が調和し、しっかりとした余韻を感じられる仕上がりとなっています。
長野県のおすすめワイン
日本の気候のもとでは、ボルドーのように力強い赤ワインというのは現状あまりつくられていません。それでもそういったワインが好みであるなら、まず長野県で探すのがいいでしょう。メルローやカベルネ・ソーヴィニヨンでも非常に高品質なものが見つかります。特に桔梗が原地区は「日本のグラン・クリュ」と言われるような、非常に恵まれた栽培環境です。
執筆時の当店のラインナップにGI長野の認定を受けたメルロー単一ワインの取り扱いはありません。しかし上記のような日本で他にあまりないワインの雰囲気は、こちらのリーズナブルなワインからも少し感じていただけます。
主要なワイナリーの一例
小布施ワイナリー、ヴィラデストワイナリー、サンクゼール、安曇野ワイナリー、Kidoワイナリー、信州たかやまワイナリーなど
GI山形|フルーツの王国
山形県はブドウに限らず様々なフルーツの栽培が盛んな地域。デラウェアやマスカット・ベーリーAが主要品種です。
自然的要因
山形県は奥羽山脈や出羽山地などの山々に囲まれ、県内を縦断する最上川とその支流が形成する盆地が点在しています。これにより昼夜の寒暖差が大きく、ブドウの成熟に適した環境が整っています。また、山の斜面を利用したブドウ栽培は、水はけの良さと十分な日照を確保でき、高品質なワイン用ブドウの生産に寄与しています。
人的要因
山形県のブドウ栽培は江戸時代に遡り、明治時代には果樹試験場の設置により欧州種や米国種の導入が進み、県内各地でワイン醸造が盛んになりました。昭和59年には山形県ワイン酒造組合が設立され、定期的な品質審査や技術研鑽を通じて、地域全体のワイン品質向上に努めています。
ワインの特性
GI山形のワインは、ブドウ本来の味や香りが引き立ち、爽やかな酸味が特徴です。白ワインは華やかな花や柑橘系の香りと豊かな酸味を持ち、赤ワインは果実由来のアロマと穏やかな渋みが調和しています。ロゼワインはフルーティーで軽やかな味わいが魅力です。
GI山形のおすすめワイン
山形のワインを飲むなら、まずはマスカット・ベーリーA、そしてシャルドネに注目頂きたいと考えます。
老舗ワイナリーであるタケダワイナリーのスタンダードな1本には、主要品種のデラウェアとマスカット・ベーリーAを両方使った、少し珍しい1本。味わいのコクに黒ブドウを感じます。
シャルドネとしては高畠町の「高畠ワイナリー」が、世界と戦えるクラスのシャルドネをつくっており、抜群の知名度を誇ります。
主要なワイナリーの一例
朝日町ワイン、酒井ワイナリー、蔵王ウッディファーム
GI大阪|デラウェアの品質と歴史を評価
大阪府は東京都に次いで食料自給率が低く、決して農業の盛んな地ではありません。先述の通りワイナリーもワイン生産量も少ないのにGI認定されたのは、特にデラウェアからつくるワインの品質と歴史が評価されたからでしょう。
自然的要因
大阪府は年間を通じて天候が安定しており、特に夏季の降水量が少ないため、ブドウの健全な生育に適しています。この気候条件により、味に厚みがあり美しいブドウが安定して収穫されます。
人的要因
1880年頃から大阪府は食用ブドウの主要産地として発展し、規格外の食用ブドウを活用するためにワイン醸造が始まりました。ワイン製造者は食用ブドウ栽培で培った技術を活かし、欧州種のブドウ栽培にも取り組んでいます。また、大阪府立環境農林水産総合研究所や地域のワイン製造者が連携し、醸造技術の向上を図っています。
ワインの特性
GI大阪のワインは、食用ブドウとしてもなじみのあるデラウェアからつくられるワインで高く評価されています。凝縮された果実味と穏やかな酸味、ほどよい旨味を感じることができ、心地よい余韻が残る、食との相性が良いものと評価されています。
大阪府産のおすすめワイン
大阪府のワインをまず飲むなら、デラウェア一択。食用ブドウとしての栽培も多く、リーズナブルに楽しめます。
主要なワイナリーの一例
フジマル醸造所、河内ワイン、カタシモワイナリーなど
輸入ワインと比べた日本ワインの楽しみ方
このブログをお読みいただいているような方の多くにとっては、ワインはまず輸入品が当たり前であり、日本ワイン"も"あるという認識でしょう。
輸入ワインを普段飲んでいる人にとって、日本ワインをあえて選ぶ理由はあるのでしょうか。
気候と土壌に由来する日本ワインの特徴
日本はブドウ産地として高温多湿で雨が多く、しかもブドウ生育期に雨が降る気候です。しかも栄養分に富んだ粘土質などの土壌が多く、ブドウの樹が成長しやすい環境です。
どちらもブドウの品質面ではマイナス要因です。樹の成長に栄養が使われれば、質の高い実をつけづらく、地中に蓄えられた水分を吸って味が薄まります。


ゆえに日本のブドウは主要生産国のものほど糖度が上がりません。アルコール度数15%の日本ワインなんてほぼ見かけず、むしろ捕糖をしてつくるのが当たり前です。
また主要ワイン産地と比べると、昼夜の寒暖差が小さい傾向にあります。海に囲まれているからでしょう。夏の夜は暖かく、ブドウの酸味が低くなる要因となります。
柔らかく繊細、日本ワインの味わいの特徴
先述の気候ゆえ、大雑把にいえば日本ワインは全体的にアルコール度数が低めで、酸が穏やか、タンニンも控えめなものが多いです。凝縮感があってパワフルなものや、目の覚めるような酸味を持ったものは少なく、やわらかくやさしい味わいが傾向です。
高い熟成ポテンシャルを持つワインは、現時点では稀でしょう。「息子のバースデーヴィンテージのワインを20年後に」というような楽しみ方を考えるなら、輸入ワインの方が向いています。
輸入ワインと日本ワイン、それぞれの楽しみ方
日本ワインの繊細な味わいは、特に普段の夕食に適しています。栄養バランスを考えて野菜を多く使い、油脂を減らしたヘルシーな料理。そんな繊細な味付けに対して、控えめさを持った日本ワインの味わいは極めて調和します。
これは日本ワインのアルコール度数の低さが貢献しています。


もちろん輸入ワインの中にもそんな繊細な味わいのものはあります。だから晩酌用のワインとして、輸入ワインも日本ワインも両方楽しめばいいと考えます。
一方でこってり濃厚な味付けの料理を食べたいときには、輸入ワインから合いそうなものを探すのが無難でしょう。
日本ワインは安くない!?
ワイン生産国を旅行した人が、「現地で飲んだワインは安くて美味しかった」というのは、輸送費がかかっていないからです。
しかし日本で飲む日本ワインも、それほど安いわけではありません。それは純粋に生産コストが高いからです。主に栽培コストです。
高温多湿で雨が多ければ、ブドウが様々な病気になるリスクが高まります。その防除として農薬の散布が必要で、人件費とともにそのコストがかかります。それでも病気になり収穫量が減ってしまうリスクも計算しなければいけません。
また栄養豊富な土壌では草が伸び放題です。草刈りの手間もワイン生産国と比べると段違いです。


収穫前にブドウ畑にいくと、1房1房にこのような紙の傘がかけられています。雨から守るためのもので、笠かけの作業も大変な手間です。
ブドウだけでなく樹が病気になるリスクも高く、植え替えの頻度も高めでしょう。
かつては「日本は人件費が高いから生産コストが高い」と言われていましたが、今や別に日本人の給料は高くありません。それでも生産コストは高いのです。
それが輸送費が安いにも関わらず、輸入ワインに比べて割安感がない理由です。
円安の今、日本ワインの割高感はもうない
では輸入ワインに比べて高いかというと、そうとも言えなくなってきました。というのもここ数年の円安により、輸入ワインの大半が値上げを余儀なくされてきたからです。
そして日本ワインの味わいの平均レベルも大きく上昇していると私は感じています。
なので輸入ワインと日本ワインのコストパフォーマンスというのは、今やそれほど違いはない。そう考えます。
輸入ワインの中にもコスパの良し悪しがあるように、日本ワインにも価格以上の価値を感じさせてくれるものもあれば、そうでないものもある。それだけです。
10年以上前に日本ワインを飲んでがっかりした経験がある方こそ、今一度同じ価格帯の輸入ワインと比べて飲んでいただきたい。「自国のワインだから」なんてひいき目抜きに美味しいものが見つかるはずです。
GIが導く日本ワインの未来
日本ワインは日本人だけのものではありません。
総人口も飲酒人口も減っている日本の市場だけ見てては未来はない。世界の市場に対してブランディングしていくことが、これからますます重要になります。それは大手ワイナリー1社でできることではないでしょう。
「日本ワインって○○だから美味しいよね」
アメリカ人にもイギリス人にもそう思ってもらいたい。私はそう願っています。


同じ土俵で勝負しても、きっとブルゴーニュやボルドー、ナパ・ヴァレーのワインには勝てないでしょう。しかし別の味筋なら可能性があります。
繊細な料理に寄り添うような、天然の低アルコールで未熟な風味のない辛口ワイン。それが求められるシーンなら、ヨーロッパで日本ワインが選ばれる可能性もあると、筆者は考えています。
そうなったとき、「日本ワイン」という表記ルールよりもっと詳細なカテゴリが必要です。現時点でも「日本ワイン」にもいろいろあるのですから。
その役割を「GI」が果たすのか、将来的には別の表記ルールが求められるのか。いずれにせよ日本ワインの表記ルールは、未来における日本ワインの躍進を願ってつくられるものということを知っていただければと考えます






