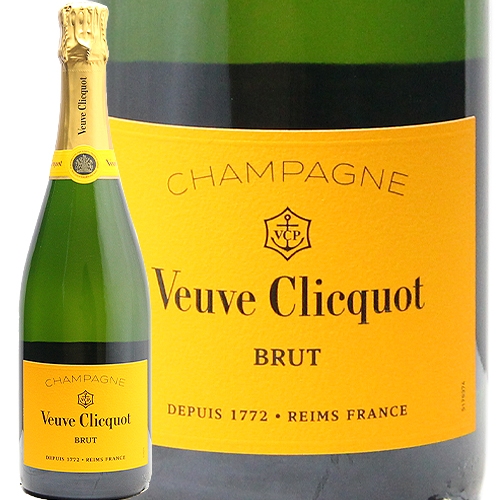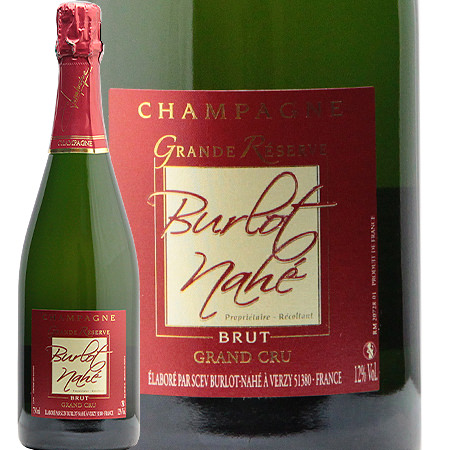愛好家が「一度は飲みたい」と憧れる有名ワインのほとんどは、名前だけじゃなく味も抜群。
一方でその値段は類似するものを大きく上回ることも多く、「ブランド料」が乗っていると感じることも。
ブランドが大事なシーンもありますが、自分で買って飲むなら純粋に味とコスパを重視したい。
有名ワインの良さを認めるとともに、代わりとして提案したい似たスタイルのワインをご紹介します。
有名ワインはなぜ有名か
見たことがある。名前を聞いたことがある。飲んだことがある。それが美味しかったというぼんやりとした記憶として残っている。
そんな人がたくさんいるのが「有名なワイン」です。SNSなどでも目に触れる機会が多いことでしょう。
ワインの仕事に就いたばかりで、知名度の高いワインは一度飲んで勉強したい。
最近ワインにハマり始めてまだ自分の好みもわからないから、昔から評価が高く人気のワインから飲んでみよう。
その気持ち、非常に分かります。
そういったワインはなぜ有名か、考えたことがありますか?
有名ワインに関する人気記事▼
ワインが有名になる経緯
ワインの品質が高く美味しければ勝手に有名になっていくほど、簡単なものではありません。なぜなら人々の好みは多様だから。そして美味しいワインは世の中に既にたくさんあるからです。
既に知名度のある生産者が新しく立ち上げたブランドだから、最初から世界中の期待値が高く、その期待に応えてきたから有名。そういう例もあります。
しかし他の多くは、ワイナリーや販売者の地道な努力で時間をかけて知名度を得てきたものでしょう。そのためには消費者の期待を裏切らない安定した品質と時間は必須です。「このワイン美味しかったよ」の身近な人への口コミは、ゆっくりと、しかし着実にワインの知名度を上げていきます。

加えてワイン評価誌の影響も少なくありません。信頼の厚いメディアが高評価したがゆえに、短期間で有名高級ワインになった例もあります。
そういった受動的な理由だけでなく、ワイナリー自身や消費国の輸入会社によるプロモーションも重要です。日本でワインのテレビCMはほぼ見ませんが、雑誌の広告掲載は珍しくありません。ときにオーナーや醸造家、マーケティング担当が来日してのセミナーなどもプロモーション活動です。
ワイン評価誌の高得点で認知が広がるのは、プロや一部のディープな愛好家のみです。口コミで知られていくのには長い時間がかかります。費用をかけてのプロモーションは、より多くの消費者に短期間で認知してもらうことができます。
有名ワインはたいてい美味しい
このようにして多くの消費者に知られているワインというのは、一定以上の品質を伴っています。
人に教えたくなるほど美味しくなければ、口コミで広がっていくことはありません。評価誌の高得点は品質の証です。たくさんの人に継続的に飲まれていないと、プロモーションに多くの費用をかけることはできません。
有名ワインは有名というだけで、だいたい美味しいと言っていいのです。(例外もあります)
かといって逆は間違い。「このワインの名前は知らないし、知名度も低そうだから美味しくないだろう」と判断するのは早計です。世の中には"これから"知名度が上がっていくだろうワインがたくさんあります。
知名度にはお金がかかる?
ワイン好きの多くが知っている有名ワインは、高価なものが多いように感じます。同地域・同スタイルのワインと比べても割高であることがほとんど。
「高品質だから有名となり、知っている人は値段を上げても購入する」と考えることもできます。
一方で「ワイナリー主体で積極的にプロモーション活動を行っているから有名で、その費用は値段に乗っている」というのも事実。そのプロモーション費用の分、同程度の品質のワインより割高です。
小さなワイナリーがつくる評価の高い希少なワイン。その場合はプロモーション費用はないかもしれない。しかしその場合は中間業者が利益率を高めに設定している場合が多いです。
当店のほとんどのワインは、価格競争のために定価より安く販売しています。一方で例えば人気の高い「コングスガード」というナパ・ヴァレーの生産者。そのシャルドネは入荷数が非常に少なく割り当て制であるため定価販売です。
自分で飲むなら知名度はいらない
有名なワインを飲みたい。有名なワインである方がいいというシチュエーションもあります。
でも一人でや配偶者と家飲みするなら、知名度より味とコストパフォーマンス優先じゃないですか?

有名なワインは高額で手が届かなくとも、同じようなスタイル、ほどほどに近い品質でグッと手頃な価格。自腹で買って飲むならそんなワインがいい。限られた予算でワインを楽しむ方ならきっとそう考えるはず。
もし私が購入して飲むなら、有名なAより知名度の高くないBがいい。そんなワインをご紹介します。
「オーパス・ワン」の代わりにこれを飲む
アメリカワインのみならず、ワイン全体の中でも特に知名度の高いワインである「オーパス・ワン」。
ナパ・ヴァレーでつくられるカベルネ・ソーヴィニヨンを主体にしたボルドーブレンドの赤ワインです。
10年前は3万円ちょっとというイメージだったのですが、今では7万円前後で販売されています。ある程度供給量が多いので、酒販店が価格競争をした上で、この価格です。当店はその競争に負け気味です。。。値下げ合戦についていけない。
オーパス・ワンの優れた点ト
ナパ・ヴァレーの陽性な果実味と凝縮感があり、今から美味しく飲める。それでいて風味に押しつけがましさがなく、凛とした佇まいであること。それがオーパス・ワンの良さだと私は感じています。
ナパのカベルネには、もっとパワフルで迫ってくるようなワインもあります。それに比べると適度に控えめ。上品さだけを求めるならボルドー5大シャトーでいいわけで、それと比べたときは親しみやすさで優ります。
私ならオーパス・ワンの代わりに"南アのオーパス・ワン"
オーパス・ワンと味のスタイルが似ているワインというのは、割とあります。なのでオーパス・ワンとの関連性も含めて提案するのがこちら。価格はおよそ1/4です。
オーパス・ワンと同様にジョイントベンチャーとしてスタートした「ヴィラフォンテ」。
栽培にはオーパス・ワンの元栽培責任者であるフィル・フリーズ氏を起用しています。


南アフリカの安い人件費を活かして、選果にはかなりの手間をかけています。それゆえ味わいの透明感、整ったイメージは抜群。基本は自然酵母発酵ですが、そのニュアンスは全く感じません。カベルネ・ソーヴィニヨン主体のブレンドらしく、上品に伸びていく酸味が心地よいワインです。ボディ感はオーパス・ワンよりも少しだけしっかりしているイメージ。
強いて劣る点を挙げるなら、香りの質から受ける「洗練されたイメージ」。これはオーパス・ワンの方が気品に溢れるように感じます。
シャンパン「ヴーヴ・クリコ」の代わりにこれを飲む
LVMHグループ傘下の大手シャンパンメーカーであるヴーヴ・クリコ。シャンパーニュ地方の歴史とともに語られるような由緒ある生産者です。
ラインナップの中でフラッグシップワインに据えられているのが、この「イエローラベル ポンサルダン ブリュット」。
ヴーヴ・クリコの優れた点
このような大手メゾンがつくる定番シャンパンに共通する点として、際立った味の特徴がないことが挙げられます。「シャンパンらしい香り、シャンパンらしい味わい」こそが求められるからで、このイエローラベルもそのニーズに間違いなく応えています。
ピノ・ノワール主体のムニエ、シャルドネのブレンドですが、力強さは出すぎず、繊細な口当たりにまとまっている。いつ飲んでもイメージ通りの味であることが魅力です。
LVMHグループ。ルイ・ヴィトンを始め世界の名だたる高級ブランドを擁するグループは、世界一といっていいほどマーケティングの上手い企業です。ヴーヴクリコを味で差別化して消費者にアピールすることはできませんし、やっていません。「ヴーヴクリコのあるラグジュアリーな時間・空間」というものをプロモーションしているように感じます。彼らはシャンパンを売っているのではないのです。
私ならヴーヴクリコの代わりにこの特級シャンパン
大手メゾンであるヴーヴクリコは、その生産量の多くを購入したブドウで賄っています。その一方でシャンパーニュ地方の特級格付けの村ほぼ全てに自社畑を所有しています。「良いシャンパンは良いブドウ、良い畑から」他の生産者に先駆けてそれに気づいていたのです。
そういった高品質なブドウは、イエローラベルにはおそらくほとんど使われません。より高級な「ラ・グランダム」や「ヴィンテージ」に使われるはずです。
そこで提案したいのがこのシャンパン。
もともとはブドウ栽培家だった「ビュルロ・ナエ」が、自社でもシャンパンをつくり始めたもの。特級格付けのヴェルジィ村に5haの畑を持ち、収穫量の8割をヴーヴクリコに販売しているといいます。
「ヴーヴクリコにブドウを提供している」ということに誇りを持っており、ワイナリーの玄関にはヴーヴクリコのボトルが飾ってあるのだとか。


残りの2割でつくるシャンパンの1つがこちらですが、そのブドウは一番いいところのものです。なにせブドウの売却額は重量当たりなので、自分たち用にいいところを残すのは当たり前。
そのブドウ品質ゆえか、「イエローラベル」よりもシャンパンの旨味感やコクが強く、余韻が長く伸びます。より飲みごたえのある味わいです。
ヴーヴクリコはリザーヴワイン、昨年以前の収穫で貯蔵していたワインのブレンド比率が高く、より複雑さを持ちます。「シャンパンらしさ」とバランス感ではイエローラベルが勝るかもしれません。
そりゃあ醸造技術はヴーヴクリコの方が上です。でも「ブドウ品質なら3倍の値段のラ・グランダム相当」と思って飲むと、より記憶に残る味わいとなるでしょう。
高くなってしまったシャブリの代わりにこれを飲む
上記2つと違い、「シャブリ」は1銘柄のワインを指す言葉ではありません。ワインの生産地区名であり、そこでつくられるワインの規格と言えます。
だから「神戸牛」と言ってもその中にいくつものグレードとそれぞれの牧場があるように、シャブリも数多の生産者がつくるいくつかのグレードがあります。
今回替わりのワインを提案するのは、「シャブリ」と聞いて多くの人が一般的に想像する、スタンダードの「Chablis」です。
スタンダードの「Chablis」が好かれる理由
一番は安心感でしょう。「シャルドネでつくられるスッキリ辛口の白ワイン」そのイメージが昔から定着しているので、注文すればイメージ通りのものが飲める。名前が短くて覚えやすいことも一役買っています。
スタンダードのシャブリはオーク樽熟成を行わないか、あまり樽香を効かせず醸造されることが多いです。だから香りが強すぎないため、料理の邪魔をしにくい。とりわけ魚介料理がよく登場する日本の食卓にフィットしやすいのです。
料理とのペアリングを考えずとも、とりあえずシャブリであれば大失敗はしない。その便利さが愛される理由の一つ。
そして数年前までは2000円台で豊富な種類が手に入ったことが挙げられます。
高くなってしまったシャブリ
2021年の大凶作や世界的なブルゴーニュワインの需要増、ウクライナ戦争、なにより円安・・・。
様々な理由により、ここ5年ほどで一般的な「シャブリ」は体感で5割前後も値上がりしています。2000円台前半で手に入っていた銘柄が、3000円台半ばになったイメージ。ちょっと上級の生産者になると、スタンダードクラスが5000円前後です。
「毎日の晩ごはん時に気軽に開ける」という飲み方には、なかなかフィットしにくくなってきているのでは。
他のワインも値上がりする中で、「シャブリだけがコスパが悪い」とは申しません。依然として安定感のある美味しいワインです。
でも「同じような飲み方ができる、2000円台の白ワイン。他にないのかな?」と探し始めている方も多いのではないでしょうか。
私ならシャブリの代わりにヴィーニョ・ヴェルデ
〇シャブリのように繊細でフルーツ感が強すぎないスッキリとした味わい
〇シャブリのようにミネラル感をハッキリ感じる
〇シャブリのように魚介を始め幅広い料理の邪魔をしない
このような特徴を持つワインとして、私ならこのワインを買います。
ポルトガルの白ワインとして有名な「ヴィーニョ・ヴェルデ」。ただしこのワインは、微発泡でもなければほのかな甘みもないスッキリ辛口です。(厳密にはヴィーニョ・ヴェルデは名乗れません)
アルバリーニョ100%でつくったなら、シャブリと比べて果実味豊か、ボディしっかりとなるでしょう。こちらは土着品種の「ロウレイロ」をブレンドしているため、風味はやや控えめで軽やかです。
聞いたところ、キンタ・ド・エルミジウという生産者はシャブリが好きで、このワインもシャブリを意識した味づくりをしているのだとか。
「味がそっくり」とまでは申しませんが、知名度と安心感以外の「シャブリ」の役割は十全に果たしてくれるでしょう。
安くて似ているワインを探す楽しみを
有名なワインには有名である理由、みなが称賛する理由があるものです。例えばプレゼントのような用途には、知名度があった方がいい場合も確かにあります。
でも自分で買って飲むなら、安くて美味しいに越したことはない。みんなが知っているあのワインに似ていて、同じくらい美味しくて手頃なワインがあるとしたら。それって多くのワイン愛好家が知りたいことなはず!


もしそんなワインを見つけたら、ぜひ友人・知人に教えてあげましょう。一緒に飲み比べるのも楽しい。「ほんとだ!すごいね!」となるかもしれませんし、ひょっとしたら「全然違うじゃん!」って反応が返ってくるかも。
そんな失敗も含めて親しい人と感覚を共有するチャンス、ワインを一緒に楽しむ機会が生まれると考えると、ワクワクしませんか?