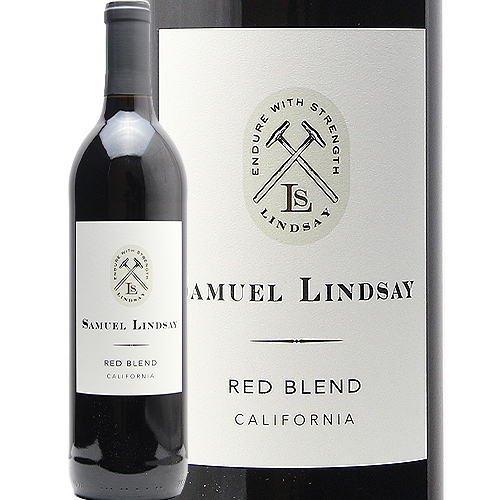ワインの説明でよく目にする「果実味」という言葉、なんとなくスルーしていませんか?この言葉の使われ方を知ると、文字から味わいをより具体的に想像できるようになります。たくさんあるワインの中から、自分好みの1本を見つけやすくなるはず。今回は、そんな「果実味」について、基本からわかりやすくご紹介します。
ワインによく出てくる「果実味」って何?
端的に述べるなら、「果実味」とはワインの香りや味わいに感じるフルーツに似た風味のことです。
ワインの説明を見ていると、よく目にする「果実味」という言葉。「果物の味がするってこと?甘いの?フルーティと何が違うの?」と、もやっとしたことはありませんか。 実はこの「果実味」という言葉は、ワインの味わいや印象を伝えるうえでとても重要なキーワードです。ここではその意味や使われ方を、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
果実の味がするわけではない?
まず、勘違いされやすいポイントから。「果実味」といっても、果汁やフルーツそのものの甘さが口に広がるわけではありません。あくまで果物を思わせる香りや、口の中で広がる風味、その味わいから感じるブドウの熟度を伝えるための言葉です。

一例を挙げると赤ワインならイチゴやカシス、ブラックチェリー。白ワインならレモンやリンゴ、パイナップルなど。ワインの香りや味わいを言葉で伝えるために、このようなフルーツに例えられます。
とはいえ、こうしたフルーツの名前がワインの説明に書かれていても、実際に果物が入っているわけではありません。 「パイナップルの風味」や「白桃の香り」といった表現は、あくまで香りや味の印象を伝えるための比喩です。ブドウの糖分が発酵してワインになる過程で、このような香りが出てくるのです。
ワインを飲んだときに「あ、なんかフルーツっぽいな」と感じたら、それがまさに果実味です。
「ある/なし」ではない「果実味」という表現
実は、果実味はすべてのワインに備わっているものです。ただ、それがはっきりと感じられるかどうかに違いがあります。
果実の香りや甘やかさが前に出て、わかりやすく感じられるワインは「果実味が豊か」「果実味が前面に出ている」などと表現されます。 このタイプのワインは親しみやすい印象があり、「フルーティー」という言葉で紹介されることもあります。

一方で果実の印象が控えめで、香りの主役がハーブ、スパイス、木樽のニュアンスなどがメインのワインもあります。 これらは「果実味は控えめ」と表現され、複雑で高級感があり落ち着いた風味を持つことが多いです。
どちらが良い・悪いというわけではなく、それぞれに異なる魅力があります。果実味の豊かさは、自分の好みに合ったワインを選ぶためのヒントになります。
「果実味」に相当する英語は何?
英語で「果実味」を表す言葉はいくつかありますが、よく使われるのは “fruitiness” や “fruit-forward” といった表現です。
“fruitiness” は香りや印象の甘やかさを中心にした表現で、“fruit-forward” は「果実の風味が前面に出たタイプのワイン」として、果実味豊かなワインによく使われます。
ただし、日本語の「果実味」は香り・味・全体の印象などを含んだやや感覚的な言葉なので、完全に一致する英語表現はありません。 「英語ではこう言うけど、ニュアンスは少し違う」という認識を持っておくと便利です。
「果実味」が分かるとワインがもっと選びやすくなるかも▼
実際のワインで理解する「果実味」という言葉の意味
ワインの紹介文やテイスティングコメントでは、「果実味」という言葉がよく登場します。 その使われ方はさまざまで、「~~な果実味」「果実味が~~で…」といった形で、香りや味わいの印象を細かく表現しています。
でも、そうした表現を読んで「なんとなくはわかるけれど、具体的にはよくわからない」と感じたことはないでしょうか。 ここでは、よくある「果実味」の使われ方を例に取りながら、書き手がどんな風味を伝えようとしているのかを、実際のワインに近いイメージで解説していきます。
「果実味豊かでジューシーな味わい」とはどんなワイン?
「果実味豊かでジューシー」という表現は、文字通り甘いフルーツのような香りをハッキリと感じるときに使います。
グラスに注いだ瞬間から、イチゴジャムやプラム、ラズベリーのような香りがふわっと立ちのぼります。一方でフルーツ以外の風味は控えめで、複雑さはありません。「フルーティー」という言葉が使われる例もあるでしょう。 まるで熟れた果物をかじったときのような印象で親しみやすく、赤ワインなら渋味が控えめなことが多いです。
表記されるヴィンテージからあまり経過していない若いワイン、それも比較的リーズナブルなものに使われます。例えばこちらのワインなどがその典型でしょう。
「熟した果実味」の反対とは?
「熟した果実味」という表現は、甘味の強いフルーツに例えられるときに使われます。
赤ワインならばブラックチェリーやダークプラム、あるいはレーズンやプルーンのような、強い甘味を持つフルーツ。白ワインならばメロンやマンゴー、パイナップルに例えられるときです。
例えばこちらのワインからはブラックベリーやダークチェリーの香りを感じます。スーパーなどでよく売られている果物ではないので、想像はつきにくいかもしれません。赤いアメリカンチェリーの風味と比較するともっと熟してそうだから「ダークチェリー」と表現するのです。
その逆で甘味の少ないフルーツに例えられる場合。赤ワインならラズベリーやカシス、白ワインならレモンやリンゴに例えられることも多いです。「未熟な果実味」と言っては印象が良くないので、特に用いられる表現はありません。あえて言うなら「酸味主体のフルーツ」などでしょうか。
熟度が低いからといって、決して悪いワインというわけではありません。上品な酸味を持つスッキリとしたワインであることを示しています。
これはブドウの熟度、ひいては畑の気候を反映しています。熟した果実味を感じる場合、非常によく熟したブドウからつくられるワインであることを意味します。そのイメージどおり甘いワインであることもあれば、辛口でアルコール度数が高く飲みごたえのワインであることもあります。
こういったワインはブドウが熟しやすい暖かい産地や、生育期に雨が降らない乾燥した産地のものが多いです。ワインの味わいや風味表現から、こういうワインの生い立ちも読み取れるのです。
「凝縮感のある果実味」とは?
「凝縮感のある果実味」と書かれているとき、言葉で表すのは難しいのですが、香りの濃さや風味のち密さを表します。香りの立ち方が強く、果物の印象も熟していて、ひと口ごとに飲みごたえを感じるタイプのワインです。
この「凝縮感」は、ブドウがどれだけしっかり成熟したかによって生まれます。ブドウの成熟度と言っても先ほどの「熟した果実味」とは違い、必ずしも甘いフルーツを意味するわけではありません。涼しい産地で丁寧に時間をかけて栽培したブドウは、酸っぱいフルーツの風味ながら非常に香り豊かです。


また高級ワインの場合には、この凝縮度のある果実味以外にも様々な香りを持つ場合があります。そういう場合はあまり「フルーティー」という印象は持たないでしょう。
このワインなどは確かに甘く熟したフルーツの香りも感じるのですが、他にも複雑な風味があり、「果実味豊かでジューシーな味わい」より高級感があります。
「果実味が控えめで繊細な風味」のワインは美味しいの?
「果実味豊かな」ワインの対義語は、「果実味控えめ」と表現することが多いです。
「果実味が控えめ」と聞くと、「味が薄いのかな?」と感じてしまうかもしれませんが、それは誤解です。 フルーツ以外の風味の方を主体に感じることを意味します。


例えば岩や土、鉱石を想わせるような香り。様々なスパイスや紅茶。熟成したワインなら皮革や枯れ葉など。
文字で見るとあまり美味しそうには思えないかもしれませんが、こういったワインには何とも言えない「深み」のようなものを感じます。
「果実味=わかりやすい美味しさ」に対して、「果実味控えめ=繊細さや複雑さが魅力」となるタイプのワインです。 ワイン初心者の方には後回しにすることをおすすめしますが、筆者は大好きです。こういったものの中には10年、20年と熟成して格段に美味しくなるものもあります。
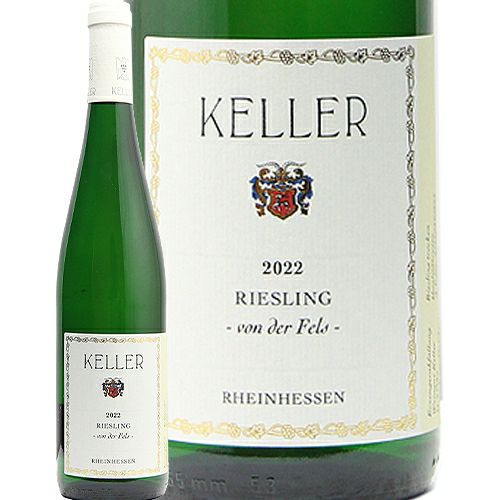
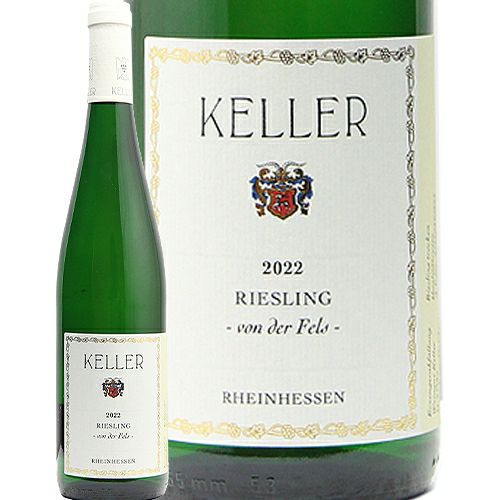
ケラー フォン デア フェルス リースリング 2022
完売 販売時¥10,560
このケラーのワインは、若いうちに飲んでも明確なフルーツの風味はあまり感じられません。なんとも言えない土や石の香りと厳しい酸味。ポテンシャルを感じるものの、誰にもおすすめできるものではありません。
「果実味」という言葉を知って、あなたのワイン選びはどう変わるのか?
ここまでで「果実味」という言葉の意味とその具体的な使い方をご紹介してきました。ではそれを知ることで、実際にワインを選ぶとき、どんなふうに役立つのでしょうか?
具体的な3つのシチュエーションで考察します。
ワイン初心者にとって親しみやすいワインとは?
もしあなたがワインを飲み始めたばかりの初心者で、特に赤ワインの中には口に合わないタイプがあると感じているとしましょう。なるべく好みにあうものだけを買いたいですよね。


それなら「果実味豊かでジューシー」に似た表現をされる赤ワインを選ぶといいでしょう。この表現がされていれば、ワインは次のような味わいであることが多いからです。
○明確なフルーツの風味を感じる
○果実味以外の風味は控えめ
○酸味がそれほど高くない
○渋味は穏やか、もしくはほとんど感じない
○価格も手を出しやすい
つまりワインに不慣れな方にとっても苦手としにくい味であり、親しみやすく感じる可能性が高いのです。もしあなたが渋味なども平気な人であっても、ワイン初心者の方と一緒に飲むときは、こういう選び方をしてみるといいでしょう。
ワイン上級者に贈るなら「果実味」と書いてないもの?
前提として万人が美味しいというワインはありません。加えて経験値でワインの好みは変わります。
ワイン初心者にとっては「分かりやすくて美味しい!」と感じる、果実味豊かなワイン。一方で、「果実感ばかりで甘く単調に感じてしまう」と思う人もいます。とりわけフランスのボルドーやブルゴーニュといった有名産地のワインを、何十年と飲んできた上級者の方に多いように感じます。そういった銘醸地の高級ワインほど、シンプルなフルーツの香りというのはあまり目立ちません。


では「果実味」という言葉が表現に使われていないような、フルーツの風味は控えめなワインならピッタリか。上級者はみな大喜びするのかというと、それも確たることは言えません。
何が言いたいかというと、「果実味の豊かさ = 美味しさ」ではなく、好みは人それぞれだということ。あなたの美味しいは必ずしも誰かの美味しいと同じではないということです。
ですのでプレゼントにワインを選ぶなら、もし可能ならばあらかじめ好みを聞くのが一番です。
みんなで飲むワインを選ぶときのヒントに
およそ5~10人で集まって飲むような場に相応しいワインを選ぶのは、自分の好みに合わせるのとは違った難しさがあります。
考え方は、なるべく苦手とされないような味で、少量でも満足感のある味わいを選ぶこと。そのためのヒントとなるのは「果実味の凝縮度」です。


「凝縮した果実味」のように味わいが表現されるワインは、高い熟度のブドウをつかっています。そうすると酸味は控えめか、もしくは酸はあっても目立たないようなボリューム感があります。「酸っぱくて苦手」と感じられる恐れは少ないでしょう。これは赤ワインでも白ワインでも言えることです。
アルコール度数が高めなことも多く、一人当たりの量が少な目でもしっかり記憶に残る味です。
ただし凝縮度の高い赤ワインの中には、力強い渋味を持つものもあります。ワインに不慣れな人は赤ワインの渋味を苦手とする方が多いでしょう。商品説明に「しっかりとしたタンニン」などの表現があれば、注意しておくとよいでしょう。
「果実味」を知って好みのワイン選びを
ワインの風味表現には他では見かけない言葉も多く、何を伝えたいのかよくわからず小難しく感じてしまいがち。「果実味」という言葉もその一つでしょう。
間違いないのは、その小難しい味わい表現も、味わいを伝えるために使われているということ。その美味しさを誰かに分かってもらいたくて、味わいを想像することで自分好みかどうかを判断できるようにと思って、そのように表現しているのです。
「果実味」という言葉は、ワインを表現する上でかなり頻繁に使われます。
どのような使われ方をするのか、どんな味わいを指しているのかを知っていけば、思った通りのワインを買って楽しむための助けになるでしょう。
ワインの味わい表現についてはこちらも参照▼