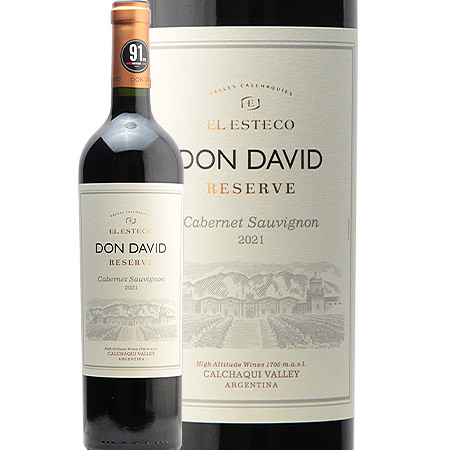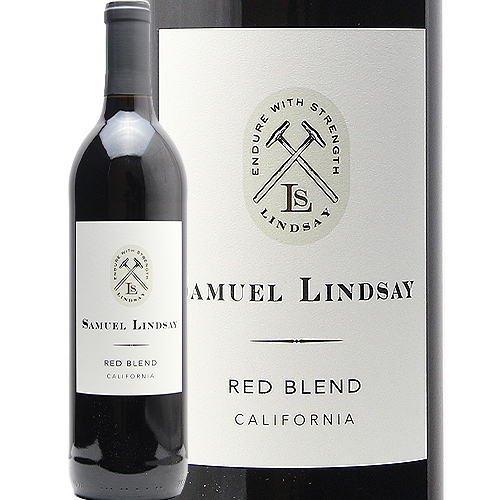1000円台の赤ワインは種類がとても豊富。コスパのいいものを選ぶにはコツが必要です。今回は「品種や産地の特徴を感じるワイン」と「生産者のこだわりがつまったワイン」の2つの視点で、おすすめをご紹介。メリット・デメリットを知れば、”なんとなく選ぶ”はもう卒業!普段の晩酌用にだって、納得の1本を選べるわたしになりませんか?
多すぎて困っちゃう!コスパのいい赤ワインの選び方
普段の夕食時に家で飲むワインとして、1000円台なら無理なく気軽に楽しみやすいでしょう。需要が大きいゆえにワインの種類も豊富で、「どれを選んでいいのかわからない!」と困った経験はありませんか?
執筆時点にて、当店では約1600種類の赤ワインを扱っています。そのうち約230種類が1000円台です。
さらに楽天市場で検索すれば、およそ2万種類の「1000円台の赤ワイン」が見つかります。(重複も含む)こんなに多くの選択肢から選ぶなんてできません。
スマートに選んで晩酌を楽しむため、選定の方針やコツが必要です。
ワイン飲み始めの方に向けた記事ではありません
本記事は「ワインはあまり詳しくないけれども好きで、普段からいろいろと飲んでいる」という方のために書いております。ご紹介するワインも、「確かにこの味でこの価格なら、コスパいいね!」というもの。
ワインを飲み始めたばかりの人がとっつきやすい、いわゆる「飲みやすいワイン」とは少し違うものもございます。
興味を持ち始めたばかりの方にはこちらの記事がおすすめです▼
1000円台のワイン選びにおすすめな2つの方針
この記事では次の2つ選び方をご提案します。
1.ブドウ品種や産地の特徴を素直に表現したワインを選ぶ
2.生産者が考える「おいしい」が表現されたワインを選ぶ
それぞれメリット・デメリットがあり、あなたの嗜好に応じておすすめが異なります。詳しくご説明します。
ブドウ品種や産地の特徴を感じるワインとは
ワインについて十分な知識を蓄えれば、ボトルに表記されていることやスペックから多くの事を読み取れます。大まかな味わいの傾向は予想できると言っていいでしょう。
ただしそれは、そのブドウ品種や産地の特性を素直に表現したワインに限って。

例えば「ピノ・ノワール」というブドウ品種なら、「香り高くて軽い口当たりと上品な酸味が特徴」というように。そこに「カリフォルニア産で1000円台なら、酸味や渋味は控えめで、少し甘くフルーティーな・・・」というように予想できるのです。
こういう典型的なワインは、期待を裏切らない安心感があります。
既にお気に入りのワインはありますか?専門的な勉強をしなくとも、とりあえず産地・品種・価格の3つ。この3つがだいたい同じワインを選べば、あまり好みから外れません。
コスパの良さをどれほど感じるかは、生産者の腕や安売り具合も関係します。でも味わいのタイプとしては好みに近いので、ガッカリすることはあまりないはず。この安心感がメリットです。

一方でデメリットもあります。
あなたはきっと、同じ品種・産地でもっと高価で美味しいワインも飲んだことがあるのでは?つい記憶と比べてしまい、物足りなさを感じるかもしれません。
典型的であるがゆえに比べられてしまうのです。
ワイン選びに失敗したくない人におすすめ
あなたは赤ワインの好き嫌いがハッキリしている方でしょうか。それとも割となんでも美味しく飲めてしまう方でしょうか。
「苦手なワインはついつい残してしまう・・・」という方なら、好みのワインだけにお金を使いたいですよね。ワイン選びに失敗したくありません。
品種や産地特性の現れたワインなら、あなたの予想と期待を裏切らない安心感があります。ワイン選びに失敗したくない方におすすめな理由です。
生産者のこだわりがつまったワインとは
一方で「自分が美味しいと思う味を目掛けてつくる」という生産者もいます。
分かりやすいのがブレンドワインです。様々な品種、あるいは地区のワインを混ぜるとき、決してあてずっぽうではありません。目指す味わいのイメージがあります。そのイメージこそ生産者が考える「おいしいワイン」です。
ワインのつくり方においてより様々な工夫ができます。それゆえあなたの好みにハマるならば、先の典型的なワインを一段も二段も超える満足が得られるでしょう。これが大きなメリットです。
ただしそのカギは、生産者の考える「おいしい」があなたの「おいしい」に一致するかどうかです。その見極めが難しいのがデメリットです。
特にブレンドワインは、単純な品種の味の足し算ではありません。「おや?思ってたよりも・・・・」となる可能性があります。

なお、この2つの方針はハッキリと分けられるものではありません。
上級ワインは産地の個性を存分に表現し、低価格帯は遊び心のあるワインとしてクラス分けしている場合もあります。今回はあえてこの2つの方向性でおすすめワインを分けてみました。
いろいろ飲み比べるワクワクが欲しい人におすすめ
お気に入りのリーズナブルなワインに出会った時、あなたは「おいしい!今度はたくさん買おう!」となりますか?それとも「おいしい!今度はちょっと違うワインを買ってみよう」と思いますか?
一生かかっても飲みつくせない種類があるのです。いろいろ飲み比べて違いを感じるのが楽しいって方も多いはず。
そういう方にとってはこちらのタイプがおすすめ。品種や産地の枠にとらわれず、美味しいワインを追求しているのです。あっと驚くようなワインとの出会いもきっとあるでしょう。ただし口に合わないこともありうる「冒険」」です。だからこそワクワクしませんか?
この2つの方針を踏まえて、次の章から1000円台でおすすめの赤ワインをご紹介していきます
ブドウ品種や産地の特徴を感じるおすすめ赤ワイン4選
まずは典型的な風味を表現した、安心して手にとれる赤ワインのおすすめをご紹介します。
あわせて1000円台におけるその品種×産地のおおまかな味わいイメージを記します。このワインが気に入ったなら、似たワインを探しやすくなるでしょう。
毎年安定した濃厚さを
このワインに期待すべき点は、1000円台でやや強めの濃厚さ。そして抑えめながら確かに感じる酸味と渋味です。さらにそれが毎年変わらないことです。
エル・エステコのあるアンデス山脈の高原地帯。きわめて乾燥していて雨が降りません。水の供給を人が管理できるので、ヴィンテージ差がほとんどないのです。
一度気に入ったなら同じ美味しさが約束される。安心を求める人にとって、これは大きなメリットではないでしょうか。


カベルネ・ソーヴィニヨン×アルゼンチンの特徴
パワフルで濃厚なイメージのある品種かもしれませんが、1000円台ではそれほどどっしりとした口当たりになりません。むしろシラーズやテンプラニーリョなどに比べると控えめ。
カリフォルニア産ほど甘い樽香が前に出てくるものは少ないです。代わりにほどよく渋味を感じるので、食事時にはベター。品種特有のピーマンのようなグリーンノートは、強い日照によってかそれほどはっきりとは感じません。
スルスル飲めちゃう心地よさ
フルーツの風味たっぷりで軽快な口当たりのこのワイン。小難しさや複雑さは一切ないので、「3000円でもおかしくない!」なんて言えませんが、肩の力を抜いて飲むワインならそれでいいじゃないですか。
シンプルなベリーの風味でとってもクリアな味わい。渋味はほとんどないのでスイスイ進みます。
このワインをつくるのはレストラングループも経営する人物。「この味をグラスワインとして出せば、何杯もお代わりしてくれるに違いない!」という狙いでもあるのでしょうか。
ピノタージュの特徴
ほとんど南アフリカでしか栽培されていない品種です。味わいのタイプはいくつかあり、どっしり力強いものもつくれるのですが、1000円台にはなし。このワインのようにピュアなフルーツ感を楽しむシンプルな味わいのものが中心です。ボディが軽いので酸味はやや強めに感じるかもですが、実際は中程度。
たまに強くローストしたオーク樽で熟成し、コーヒーっぽい風味を添加した、変わったタイプもあります。
食べて飲んで楽しい食卓に
決して主役にはならないけれども、このワインがあると夕食が楽しくなる。1人よりは2人以上で飲んで欲しいのがこのワインです。
複雑で濃厚な風味があるわけではなく、ブルーベリーやラズベリーなどの比較的シンプルな風味。ちょっと酸味が高く感じるかもしれませんが、油脂をつかった料理と一緒ならそれが食欲を増進させます。このワインによって食事がもっと美味しく感じるはず。
「この料理に対してこのワイン」なんて堅苦しいものじゃない、いろいろ料理が並ぶ食卓にこそこのワインがピッタリで、脇役として優秀なのです。


モンテプルチアーノの特徴
イタリアのアブルッツォ州が中心地で、周辺の州でもちらほら。しかしイタリア国外ではほぼ聞きません。
基本はこのワインのようにフレッシュ&フルーティーな味わい。サンジョヴェーゼに比べるとタンニンも酸味も穏やかです。シンプルながら悪いところがない味わい。しかしこれは1000円台の味わいです。
もう少し高く2000円台半ばになると、新樽も使った熟成によりボディ感豊かで複雑な風味を持つものもあります。
大規模生産者の量産スタンダード
フランス南部に位置するローヌ地方は、フランスで最もボディ豊かなワインをつくる産地と言っていいでしょう。そこで「ローヌの帝王」と呼ばれるギガルは、数万円の高級品をつくる一方で、この入口となるシリーズは大変お手頃です。
香りのボリュームにも味わいの強さにも『濃さ』があり、飲みごたえあり。その分酸味は控えめに感じるでしょう。シラー中心のブレンドであり、スミレの花のような風味と確かな飲みごたえ。口当たりの厚みはワンランク上の雰囲気を醸し出しています。
「コート・デュ・ローヌ」の特徴
「Cote du Rhone」の表記があるワインは、多くの生産者にとって入口となるワイン。赤はグルナッシュ中心にシラー、ムールヴェードルのブレンドであることが多く、甘いフルーツの香りがメインで樽香もよく現れます。カベルネ・ソーヴィニヨンなどに比べれば酸味も渋味も控えめ。その分「濃厚さ」を強く感じやすいワインです。
品種をブレンドしたワインであるとはいえ、「コート・デュ・ローヌ」というワインの型が既に出来上がっているので、産地の特徴を表したワインと言えるでしょう。各社生産量が多いので、通年で入手しやすいのが魅力です。
生産者の「美味しい」を表現したおすすめ赤ワイン4選
ブドウ品種や産地の特徴がこうだからではない。
「自分はこういうワインが美味しいと考えるから」あるいは「消費者はこういう味わいを求めているだろうから」
それを目標につくっているであろうタイプのおすすめワインをご紹介します。
ちょっと甘いくらいの方がお好きでしょ?
赤ワインのタンニンによる刺激って、ワイン飲み始めのころは苦手に感じませんでしたか?
このワインは消費者が美味しいと思うだろう味、とりわけ主にスーパーマーケットでワインを買うようなライトユーザーを目掛けて味づくりがされているように感じます。
タンニンが多めになりやすいカベルネ・ソーヴィニヨンを使いながら、渋味はほとんど感じません。先ほど紹介した「ドンダビ」とはずいぶん違います。オーク樽の甘い風味とともに、おそらくブドウ由来の糖分をほんの少し残すことで、親しみやすさを加えています。
こういう味は好き嫌いは分かれるでしょうが、少なくともアメリカのライトユーザー層は大好きだそうです。そして当店でも非常によく売れています。
クリムゾン・ランチについて
これはブランド名であり、ワインをつくるのはマイケル・モンダヴィ・ファミリー・エステート。カリフォルニアのナパ・ヴァレーにて高級ワインまで幅広くつくっています。日本ではアーティストとコラボした「y by Yoshiki」ブランドのワインをつくる生産者として有名です。
一口目から風味が迫ってくるような、凝縮感が高くてリリースしたてから親しみやすい味わいが特徴だと感じています。


マイケル・モンダヴィ ファミリー
「ジューシー」って表現は魅力的ですか?
こちらも先ほどのクリムゾンランチのように、渋味を抑えて甘味を感じるような果実味たっぷりの味わいです。
完熟フルーツのような甘くみずみずしいフルーツの風味を感じる。主にそのような意味で使われる表現だとは思います。これだけ聞くと魅力的ですが、一方で「フルーツ以外の風味をあまり感じずシンプル」「ジュースを飲んでいるような感覚でワインっぽくない」と少しネガティブな意味も込めて使われることも。
このワインに関しては後者の意味を込めても「ジューシー」と表現していいはず。ワインに不慣れな人でも、小難しさ抜きに「おいしい!」と感じる親しみやすい味わい。それを3つのブドウをブレンドすることで目指しているのでしょう。
このワインを飲んでもしも「最初は美味しく感じたけれど、途中から進まないな」と感じたとしたら、酸味の低さが原因です。冷蔵庫でちょっと冷やす、あるいは氷を一つ入れることで、よりスッキリと楽しめるでしょう。
コンティ・ゼッカについて
「コンティ」とは侯爵のことであり、500年以上続くゼッカ侯爵家が営むワイナリー。それを聞くとすごそうですが、つくっているのは味わいの面でも価格の面でも手に取りやすいワインばかりです。南イタリアにあるプーリア州にさんさんと降り注ぐ太陽。それを想わせる完熟フルーツの風味が、コンティ・ゼッカがつくるワインの特徴でしょう。


ブレンドを避けるのはもったいない!?
知名度のない手頃なワインにおいては、どうしても複数品種を使ったブレンドワインより、単一品種のワインが人気です。先述の通り味わいが想像しやすいからでしょう。しかしブドウ品種のみを頼りにワインを選んでいては、このワインのようなコスパ抜群の1本を見逃すかもしれません。
この価格帯のカリフォルニアワインについて、コスパの指標は「いかに香り高く濃くて飲みごたえがあるか」というのが一つでしょう。その点で同シリーズのカベルネ・ソーヴィニヨンにずっと勝ります。
それはきっとシラーとプティ・シラーの補助品種がいい仕事をしているから。単一でつくっても大して売れないだろう品種ですが、脇役としてボディ感を補強しコクを与える仕事が素晴らしい。
シリーズ5種類が輸入されていますが、私は試飲会で並べて飲んで、このレッドブレンドがコスパ最強だと感じました。
サミュエル・リンゼイについて
「サミュエル・リンゼイ」というのは過去の人物であり、こういう名前の人物がワインをつくっているわけではありません。ブランド名です。きっとどこか大きな会社が手掛けているのでしょうが、見つけられませんでした。
きっとそのコンセプトは「毎日でも飲める価格ながら、品質へのこだわりを感じてもらえるようなワインをつくる」といったところではないでしょうか。一口飲めばその心意気が伝わってくるかのようです。
どうだい?これがうちのワインだよ!
「Com'e」は英語でいうなら「How」。「こんな風にうちのワインはつくってるんだよ!」という名刺代わりの1本ということです。
ヴェネト州には「ヴァルポリチェッラ」という特産ワインがあります。軽い口当たりでスムースに喉を通るリーズナブルなワインです。
コメはヴァルポリチェッラとは地区が違い、それと同じブドウ品種構成でありながら、適度に濃くてなめらかな口当たりが魅力。ベリー系フルーツの風味が、よく熟しているだけでなく、ちょっとジャムのように火を加えたニュアンスもあります。
普段飲みには「コメ」を。特別な日に複数人で飲むなら、もっと飲みごたえのある上級クラスをという使い分けはいかがでしょうか。
ヴィッラ・アンナベルタについて
家族経営ながら自社畑140ha+契約畑240haというなかなかの規模。そのスケールメリットを活かした「手頃なのに濃くてなめらか」がこの生産者の魅力です。
ヴェネト州は「アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ」というパワフルな赤ワインが有名。収穫したブドウを陰干しし、凝縮した果汁からつくります。その手法をヴァルポリチェッラのエリア以外でも実践した画期的な生産者。乾燥させたブドウを一度洗う機械を導入しています。味わいのクリアさはそのためでしょう。
お気に入りワインに一歩ずつ近づく方法
今回ご紹介したワインは、全て筆者が試飲して「この価格でこの味なら素晴らしい!」と感じたものです。なので私は自信を持っておすすめします。しかしあなたの好みにあうお約束はできません。
それほどまでにワインの味わいは多様で、人の好みは様々なのです。
あなたの好みを最もわかっているのは自分自身。大事なのは一歩ずつ好みのワインを選べるようになっていくことです。
飲んだワインは写真に残そう
酔っぱらっていると脳みそがマヒして記憶力が低下します。「このワイン美味しかった!憶えておこう」と思っても、なかなか頼りにならないものです。
だからスマホを活用する!写真に撮っておくだけでも思い出す手段として残ります。どんなワインか思い出せなくても、画像検索すればすぐ詳細が出てきますから。
「美味しかった」「イマイチだった」の記録には、スマホを使うのをおすすめします。
「口にあわなかった」の方がヒントになる
普通は美味しかったワインばかり記録に残すものでしょう。しかし私はイマイチに感じたワインも記録しておくことをおすすめします。
口に合わなかった理由の方が、好みのワインを選ぶヒントになることが多いからです。


美味しいにも美味しくないにも理由があります。しかしどうしてそう感じるかを言語化できるかは別問題。そんなとき、「飲みづらく感じる理由」の方が明確に分かることが多いのではないでしょうか。
「好きな食べ物」よりも「嫌いな食べ物」の方が答えやすいようなものです。
苦手なワインを見せて相談する
例えばワインショップに行って相談するとき、好きなワインの写真を見せて「似たようなものください」とするのは賢い方法です。そこにさらに、「でもこのワインは苦手に感じたんです」と付け加えると、より精度が高まります。
きっと「渋味が強いのが苦手でしたか?」「樽の甘い風味は好きじゃないですか?」など質問してくれるでしょう。ワインの個性は同時に苦手とされるポイントにもなり得るからです。
もちろん「たまたまそのボトルだけがハズレだった」という可能性もあるので、正確にはわかりません。でも参考にはなります。


そのワインを美味しく感じるかは、突き詰めれば飲んでみるまでわかりません。しかし苦手なタイプを避けることは結構確実性があります。
自分の苦手を把握していくことは、”あてずっぽう”や"なんとなく"じゃないワイン選びができるようになる確実な一歩です。
コスパのいい1000円台の赤ワインで快適な晩酌を
「コストパフォーマンスが高い」という言葉は、「支払った金額に対して、それを消費した満足度が高い」という意味です。
本来において「コスパがいい」というべきはお客様であり、私ではありません。私は「自分が消費者だったらそう感じる」と自信を持っていますが、あなたと私の味覚は違うからです。


だからこそ「手頃に美味しいワインを味わう」ことだけでなく、それを探して飲むことも楽しんでいただきたい。
夫婦でワインを楽しむ仲なら、「これに比べたら、3日前のワインの方がコスパいいよね」なんて話のネタにしてほしい。一人暮らしでだって、SNSに投稿して楽しむこともできます。
先述の通り、1000円台赤ワインに限っても飲みつくせないほどの数が流通しています。コスパのいい自分好みのワインを探求するワクワクを、あなたの晩酌時間に取り入れてみてはいかがでしょうか。