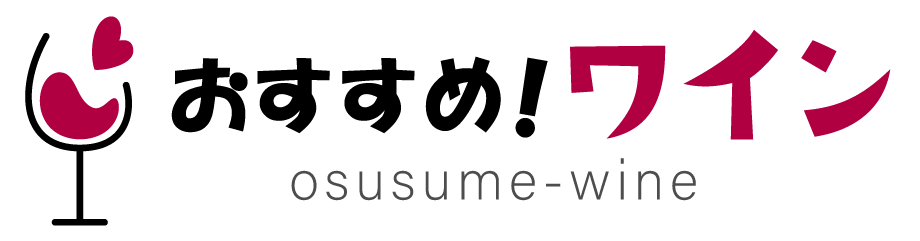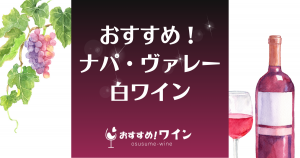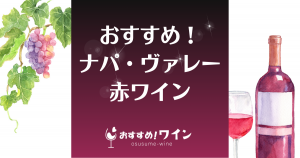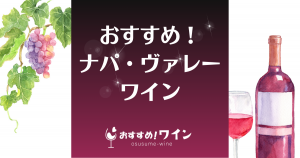本ページにはプロモーションが含まれています。
「ワインって難しいイメージ…」「ワインの味は好きだけれど、あまり詳しくない…」
ワインは産地や銘柄、年代などで、味わいが大きく異なります。
そこで、本記事ではCOCOSご協力のもと、ワインの基礎知識についてどこよりもわかりやすく解説します。
- ワインの基礎知識がわかる
- 失敗しないワインの選び方がわかる
- ワインの美味しい飲み方がわかる
また、ワインのことを学ぶには、飲みながらがおすすめ。
ワインセットであれば、飲み比べをしながらワインの世界を楽しむことができますよ。
本記事を読むだけで、ワインを飲む時間が楽しくなるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
【図解】ワインの基礎知識概要

ワインを飲むなら、まずはこの4点を押さえておきましょう。
ワインは、ぶどうを発酵させて作ったお酒です。
ヨーロッパ周辺が起源となりますが、最近ではアメリカやアジアでも作られています。
ワインには白・赤・スパークリングの他にもピンク色の「ロゼワイン」やオレンジ色の「オレンジワイン」があり、それぞれ異なる味わいが楽しめます。
ワインは、濃厚さを表す「ボディ」と味を示す「辛口」「甘口」などの言葉で表現され、選ぶ時の指標になるでしょう。
ここからは、ワインの基礎知識について詳しく解説していきます。
ワインとはぶどうがそのままお酒になったもの

ワインは、ぶどうから作られる醸造型の果実酒です。
ぶどうの自然な水分と糖分が醸造の基本となり、ぶどう単体で自然にワインへと変化していくのが特徴。
時には、味の調整のために糖や酸を加えることもありますが、製造方法は各国の法律によって厳しく管理されています。
ぶどうを醸造することにより、その味わいは大きく変わります。
食品材料を微生物によって発酵させ、さらに熟成させること。
主に酒類・味噌・醤油などをつくる工程を指す。
同一のぶどう品種でも、栽培される地域、農家やその年の気候条件によって、完成するワインは各々異なる味わいを持ちます。
ぶどうそのものの特性が直接ワインに反映され、自然との関わりの中で生じる多様な風味の深みが、ワインの魅力の一つです。
ワインはぶどうから作られる醸造酒

お酒は、使用される原料が「穀物または果実」か、そして製造過程が「発酵によるものか、蒸留によるものか」によって、大きく4つのカテゴリーに分けられます。
この分類の中で、ワインは果実を原料とする醸造酒です。
蒸留酒を作る過程では、まず発酵酒を作り、その後それを蒸留して作ります。
例えば、ワインを蒸留することによって生まれるのが「ブランデー」です。
また、様々な種類のお酒から作られる混成酒には、ハーブや果物などから抽出した成分を加えるものがあります。
日本で広く親しまれている例としては「梅酒」があります。
ワインがぶどうだけで作れる理由
ワインと同じ醸造酒には、ビールや清酒も含まれます。これらとの違いは、原料だけではありません。
ここでは、ビールを例に違いを見ていきましょう。
| 項目 | 水分 | 糖分 |
| ワイン | ぶどう自体に水分を含む =ぶどうの味がワインに影響 | ぶどう自体に糖分を含む =糖化の必要なし |
| ビール | 穀物自体に水分が少ない =仕込み水の味わいがビールの味に影響 | 炭水化物として糖分を持つので 直接発酵はできない =糖化が必要 |
アルコールは、原料の糖分が酵母により分解されることで生成されます。つまり、糖分を持たない「穀物」は、そのままではアルコールに変わることはありません。
一方で、「ぶどう」には既に糖分が含まれているため、条件が整えば、潰して放置するだけで自然に発酵し、ワインが完成します(ただし、日本では個人がぶどうからワインを製造し、それを消費することは法律で制限されているので注意が必要です)。
また、穀物からお酒を作る際には、仕込み水が不可欠で、この水の質が最終的なお酒の風味に大きく影響します。
一方、ワインはぶどうが直接変化するため、ぶどうの品質が非常に重要。
ワインの味わいの80〜90%はぶどうの品質で決まる、と言われているほどです。
ワインの主なぶどう品種6つ

世界中には、土地ごとの固有の品種を含めて数千に及ぶぶどうの種類が存在し、それぞれに独自の風味があります。
全てのぶどう品種の味の特徴を理解するのは、たとえ熟練のワイン愛好家であっても難しいでしょう。
ここでは、多く生産され、一般にも広く飲まれている主要なぶどう品種6つを紹介します。
ワイン初心者の方は、まずはこれらの品種から飲み比べてみるのがおすすめです。
さっそく、ぶどうの品種ごとの詳細を見ていきましょう。
白ワインの品種3つ
白ワインには、「白ぶどう」が使用されます。
白ワインは皮や種を使用しないため、ほとんど渋みを含まず軽やかな風味のワインが多くなります。
そのため、ワイン初心者でも楽しみやすいのが特徴です。
- シャルドネ
- ソーヴィニヨン・ブラン
- リースリング
それぞれの品種をみていきましょう。
1.シャルドネ

画像引用:COCOS
シャルドネは、日本をはじめとする世界中で広く栽培されている白ワインの主要なぶどう品種です。
この品種は、他の多くの品種と比較しても、品種そのものの風味よりも栽培される地域の気象条件や土壌の質、製造者の手法がワインの風味に大きく影響を与えます。
そのため、シャルドネは非常に多様性に富んだ表現を持ち、探究する価値のある深い品種と言えます。
2.ソーヴィニヨン・ブラン

画像引用:COCOS
ソーヴィニヨン・ブランは、香りが特徴的な品種です。
ライムやグレープフルーツ、グリーンアスパラガスのような緑色の果物や野菜、レモングラスのような清涼感あるハーブの香りを持ちます。
栽培される地域によっては、パッションフルーツのような香りが加わることも。
ぶどう本来の自然な香りや繊細な酸味を大切にしてワインが製造されることが多い品種です。
3.リースリング

画像引用:COCOS
リースリングは、あざやかな酸味を特徴とし、生産地によってはレモン、白桃、アプリコットのようなフルーツの香りに加えて、カモミールのような繊細な花の香りが楽しめます。
辛口からやや甘口、デザートワインまで幅広く高品質なワインをつくれます。
赤ワインの品種3つ
赤ワインを作るには、黒ぶどうが不可欠です。
まれに白ブドウを少し加えて発酵させる方法もありますが、赤ワイン特有のきれいなルビー色は黒ぶどうの皮によるものです。
そのため、黒ぶどうを使用せずに赤ワインを作ることはできません。
赤ワイン作りでは、ぶどうの果汁だけでなく、皮や種も全て利用します。
これらを一緒に発酵させることで、タンニンという渋み成分が抽出されます。
一般的に、タンニンが豊富に含まれるワインは、時間をかけて熟成させるとより味わい深くなり、重厚なワインへと変わる傾向があります。
- ピノ・ノワール
- メルロー
- カベルネ・ソーヴィニヨン
さっそくみていきましょう。
1.ピノ・ノワール

画像引用:COCOS
小さめの房を持ち、やや大きな粒と薄い皮が特徴。
非常に繊細で、涼しい気候の地域での栽培が好まれます。
赤い果実の香りとクリアな酸味が際立ち、洗練された風味を持つのがこの品種の魅力。
主に赤ワインの製造に使用される一方で、ブラン・ド・ノワールとしてスパークリングワインや白ワインの生産にも活用されます。
通常は単品種のワインとして使用されることが一般的です。
2.メルロー

画像引用:COCOS
タンニンが少なめで、飲み口に丸みと柔軟性があり、新しいヴィンテージでもすぐに楽しめる性質があります。
プルーンやブラックベリーのような、熟した黒果実の香りが鮮明に感じられるのがこの品種の特徴。
単独でワインを作ることもあれば、他の品種、特にカベルネ・ソーヴィニヨンやカベルネ・フランとのブレンドで使用されることが一般的です。
3.カベルネ・ソーヴィニヨン

画像引用:COCOS
粒が小さいため果皮が多く、タンニンも豊富に含まれている品種です。
若いうちは渋みが強調されますが、時間をかけて熟成すると、より滑らかな味わいに。
カシスやブラックチェリーのような濃厚な黒果実の香りが特徴です。
メルローやカベルネ・フランなど、他の品種と組み合わせて使われることが多く、ブレンドによって複雑な味わいがたのしめます。
ワインの種類と造り方
ワインには「スパークリングワイン」「白ワイン」「ロゼワイン」「オレンジワイン」「赤ワイン」という5つの主要な種類が存在しますが、基本的な作り方はあまり変わりません。
ワインの基本的な作り方はこちら。
- 収穫したぶどうから圧搾機を用いて果汁を抽出し発酵させる
(赤ワインの場合はぶどうを破砕し、果皮と果汁を一緒に発酵) - 赤ワインは発酵後に圧搾され、白ワインと同様に、タンクや樽で一定期間保管し熟成させた後、清澄・濾過を行う(この工程は行わない生産者もいます)
その後、瓶詰めを行う
※発酵に使用される容器(ステンレスのタンクや木製の樽など)や、発酵を促すために加える酵母(自然界に存在する酵母を利用するか、特定の酵母を培養して使用するか)は、製造者の手法によって異なります。
これらの工程を経ることで、それぞれのワインの特色と味わいが生まれ、多様なスタイルのワインが製造されます
ワインの味わいはボディと「甘口」「辛口」で表現される

「ボディ」という用語は、ワインの味わいで感じられる重さや密度を示す際によく使われます。
軽い感触の「ライトボディ」、中間の「ミディアムボディ」、そして濃厚な「フルボディ」という3つのカテゴリーに分けることが可能です。
また、糖度を示す「甘口」「辛口」などの表現も、ワインの味わいを表現する際によく使われます。
「ボーン・ドライ(非常に辛口)/ドライ(辛口)/オフドライ(やや辛口)/セミスイート(やや甘口)/ミディアム・スイート(甘口)/スイート(非常に甘口)」のように細かく分類され、これをワインの「ボディ」と組み合わせることで、より細かくワインの風味を表現できます。
ワインの主な産地には新世界と旧世界がある
ジョージアを含む東欧やフランス、イタリア、スペインなどのヨーロッパ諸国は、ワインの伝統を持つ「旧世界(オールドワールド)」として知られています。
そして、これらの国々から技術が伝わったアメリカやオーストラリア、南アメリカ、アジアの一部などは「新世界(ニューワールド)」と呼ばれます。
旧世界(オールドワールド)
- フランス
- イタリア
- スペイン
新世界(ニューワールド)
- アメリカ
- オーストラリア
- 南アメリカ
- アジア
現代では新世界の国々でも質の高いワインが製造されており、どちらのワインでも広く楽しまれています。
また、気候変動や醸造技術の進歩、生産者の継続的な取り組みにより、ワイン製造が従来あまり盛んではなかった地域でも、素晴らしいワインが生産されるようになってきました。
ぶどう栽培に適した気候とは?

ワインを作るぶどうの栽培には、品種ごとに適した気候があり、一般的には涼しい地域での栽培が好まれます。
暖かい地域では、ぶどうが成熟する過程で糖分と酸味のバランスを適切に保つのが難しいためです。
糖分と酸味のバランスが取れない場合、風味に欠ける、アルコール分が高すぎるワインができてしまう可能性も。
ここで重要となるのが「日較差」、つまり日中と夜間の気温差です。
例えば、アルゼンチンやチリのように日中は非常に高温になるものの、夜には大きく温度が下がる地域では、ぶどうが理想的なバランスで成熟します。
この温度差があるおかげで、果実味が濃厚でありながら、酸味も適切に保たれ、バランスの取れた味わいのワインが生産されています。
加えて、土壌の条件もぶどう栽培には大切。
肥沃すぎる土地よりも、栄養分が少ない痩せた土地の方が、ぶどうの木が水分や栄養を吸収しようと根を深く張ります。
そのため、ぶどうは土壌の様々な成分を吸収し、結果としてその土地の個性がワインの味わいに反映されることになります。
ワインの価格はどうやって決まる?
ワインの価格範囲は広く、同一品種であっても、低価格なものから数百万円に及ぶ高価なものまで存在します。
価格差の主な理由は、生産関連費用と市場の供給と需要のバランスにあります。
ぶどうのコスト、ボトルやコルクなどの包装材料費、さらには生産される国の税制や労働力コスト、そして物流費用などが、ワインの基本価格を形成する要素です。
また、特定の食材価格が上昇するように、ワイン価格も市場の変動に左右されます。
限定生産のワインや特に人気のあるワインは、高い需要により価格が上昇する傾向にあります。
高価なワインには、しっかりとした理由があるということですね。
失敗しないワインの選び方

ここまで、ワインの奥深い世界について解説をしてきました。
しかし、ワインの種類や作り方は分かっても、「結局美味しいワインって?」と悩んでしまう方もいるでしょう。
ここでは、ワインの選び方のおすすめを解説していきます。
- 価格で選ぶ
- 食材(色)で選ぶ
- 年代(ヴィンテージ)で選ぶ
それぞれ詳しく紹介していきます。
1.価格で選ぶ
まずは、シーンに応じて価格帯からワインを選ぶのがおすすめです。
例えば、ホームパーティーなどのカジュアルな食事の場であれば3,000円から5,000円程度のワイン、高級レストランでの食事なら10,000円から20,000円のワインがぴったりでしょう。
このように、食事の価格とワインの価格を合わせると失敗が少ないですよ。
レストランでソムリエがいる場合、予算や好みを伝えて選んでもらうことも良い方法です。
自宅での楽しみ方としては、3,000円程度のワインが一つの基準になります。
もちろん、1,000円未満のワインでも美味しいものは多くありますが、3,000円を超えると選択肢も広がり、高品質で美味しいワインに出会えるでしょう。
2.食事で選ぶ
日本では、肉料理には赤ワイン、魚料理には白ワインというペアリングが一般的な考え方とされてきましたが、これが常に適切とは限りません。
例えば、ピノ・ノワールのような軽めで鉄分を感じさせる赤ワインは、マグロやサーモン、カツオなどの赤身魚とも良く合います。これらの魚に白ワインを選ぶと、時に魚特有の臭みが強調されてしまうことも。
一方、鶏肉や豚肉のようなあっさりとした肉料理には、白ワインがよりその風味を引き立てることがあります。
つまり、食材とワインの色だけでなく、その味わいや質感も考慮してペアリングを考えることが重要です。
レストランであれば、ソムリエに合うワインを聞いてみるのもおすすめです。
3.年代(ヴィンテージ)で選ぶ
プレゼントやお祝い事の際におすすめなのが、年代でワインを選ぶ方法です。
ワインには、長期間熟成させたヴィンテージワインがあります。
ワインを選ぶ際に、自分や大切な人の記念年と一致するヴィンテージを選ぶことはワインならではの楽しみ方と言えるでしょう。
しかし、ワインには当たり年があり、年代だけで選ぶのは難しい場合もあります。
ヴィンテージワインを選ぶ際には、その年代でおすすめのワインをソムリエに聞いてみるのがおすすめです。
天候に恵まれた年の優れたヴィンテージや、そうでない年のものまで、ワインの性格は年ごとに変わります。
ワインには賞味期限がないため、新鮮な香りを楽しむ人もいれば、長い時間を経て熟成した風味を好む人もいます。
複数のボトルを保存し、時間の経過と共に変化する味わいを体験するのもおすすめですよ。
ワインのおいしい飲み方は?
ワインのおいしさを最大限に引き出すには、「適切な温度」と「適したグラス」の選択がとても重要です。
特に、温度設定は極めて重要です。過度に冷やすとワインの渋みや酸味が前面に出てしまい、香りも損なわれがちです。
例えば、スパークリングワインは冷やすだけでなく、少し温度を上げた状態で白ワイングラスに注ぐことで、アロマの豊かさや味の複雑さが際立つことも。
ワインの種類に合わせた温度で保存することが重要です。
また、ワインの入ったグラスを回しているのをみたことがある方も多いのではないでしょうか。
グラスを回すことでワインが空気に触れ、温度の変化によって味わいが変化します。
グラスを軽く回すことは、ワインに空気を取り込ませ、香りを引き出し味わいを滑らかにする効果がありますが、長く熟成した繊細なワインに対しては、やりすぎには注意が必要。
適度な空気の取り込みは良いものの、過剰な行為はワインの持つ特性を損なう恐れがあります。
まとめ
本記事では、ワインの基礎知識を紹介しました。
ワインには味以外にも産地や製造方法、香りなどのさまざまな違いがあります。
だからこそ、さまざまな種類のワインを飲み比べたり、自分好みのワインを探したりするのはとても楽しいものです。
本記事をぜひ、ワイン探求の旅に役立ててくださいね。